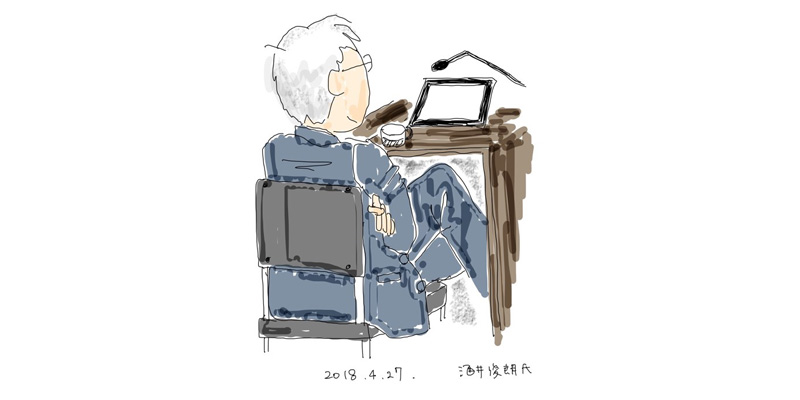
上写真:手足を組み、リラックスした様子で証言する酒井俊朗氏 絵:吉田千亜さん
「切迫感は無かった」の虚しさ
4月27日の第9回公判は、前回に引き続いて、津波評価を担当する本店原子力設備管理部土木グループ(2008年7月からは土木調査グループ)を統括していた酒井俊朗氏が証人だった。
裁判官とこんなやりとりがあった。
- 裁判官「早急に対策を取らないといけない雰囲気ではなかったのか」
- 酒井「東海、東南海、南海地震のように切迫感のある公表内容ではなかったので、切迫感を持って考えていたわけではない」
- 裁判官「15.7mが現実的な数字と考えていたわけではないのか」
- 酒井「原子力の場合、普通は起こり得ないと思うような、あまりに保守的なことも考えさせられている。本当は、起きても15mも無いんじゃないかとも考えていた」
高い津波は、切迫感がある現実的なものとは認識していなかった。だから罪はない、と主張しているように聞こえた。
東電幹部が乗用車の運転をしていて、それによる事故の責任を問われているならばこの論理も説得力を持つだろう。しかし責任を問われているのは、原子力発電所の「安全運転」についてだ。事故の死者は交通事故の数万倍になる可能性もあり、東日本に人が住めなくなる事態さえ引き起こすのである。はるかに高い注意義務がある。
そのため、普通は起こり得ないようなことまで想定することが原発の設計では国際的なルールになっている。具体的には、酒井氏が説明したように、10万年に1回しか大事故を引き起こさないように安全性を高めなければならない。
数十年間の運転中に起きる確率は低いから、その津波に切迫性は無い。あるいは、これまで福島沖で発生したことは過去400年の文書には残っていないから現実感は無い。そんな程度では、高い津波にすぐに備えない理由にならないのだ。
地震本部の長期評価(2002)は根拠がない?
相変わらず弁護側の宮村啓太弁護士の尋問の進め方はわかりやすかった。法廷のスクリーンで映し出すグラフの縦軸、横軸の読み方を丁寧に説明するなど、プレゼンテーションのツボがおさえられている。原発のリスクを示す指標である確率論的リスク評価(PRA)について、宮村弁護士の解き明かし方は、これまで聞いた中で一番わかりやすかった。PRAの専門家である酒井氏が「あなたの説明がよっぽどわかりやすい」と認めたほどだった。
そのプレゼン術で、宮村弁護士は、地震本部の長期評価(2002)の信頼性は低いと印象づけようとしているように見えた。
- 宮村「長期評価をどうとらえたのですか」
- 酒井「ちょっと乱暴だと思いました。これは判断であって、根拠が無いと思っていました」
言葉を変えながら、こんなやりとりが何度も繰り返された。
そして、宮村弁護士と酒井氏が時間をかけて説明したのが、米国で行われている原子力のリスク評価の方法だ。法廷では、酒井氏が電力中央研究所でまとめた研究報告(*1)が紹介された。
酒井氏は、どんな地震が起きるか専門家の間で考え方が分かれている時は、専門家同士が共通のデータをもとに議論することが大切であると強調した。
不思議なのは、酒井氏の研究報告が「長期評価の信頼性が低い」という弁護側主張と矛盾していることだ。長期評価(2002)は、文部科学省の事務局が集めた共通のデータをもとに専門家が議論して、地震の評価を決めている。酒井氏の推薦する方法そのものである。
一方、東電が福島沖の津波について2008年に実施したのは、個々の専門家に、共通のデータを与えることなく、意見を聞いてまわる調査方法だった。「米国では問題があるとして使われなくなった」と酒井氏が証言した方法そのものである。
酒井氏の証言には、こんな「あれっ」と思わされる論理のおかしさがあちこちに潜んでいた。
東北電力も高い津波を予測していた
この日の公判で、東電や東北電力が事故後7年も隠していた新しい事実も明らかにされた。2008年3月5日に、東電、東北電力、日本原電などが参加して開かれた「津波バックチェックに関する打合せ」の議事記録である。
これによると、東北電力の女川原発も、地震本部の長期評価(2002)の考え方に基づき、これまで発生した記録のない宮城県沖から福島県沖にまたがる領域でM8.5の津波地震を想定していた。東電だけでなく東北電力も、明治三陸沖地震(1896)のような津波地震が、もっと南で起きる可能性を検討していたのだ。この場合、女川原発での津波高さは22.79mの津波と計算されていた。
長期評価によれば、女川(敷地高14.8m)も水没すると予測されていたのである。2008年3月時点では、東電は長期評価を取り込む方向で動いていたが、それに対して東北電力は難色を示した可能性がある。
完全に手詰まりだった
「津波対策のため原子炉の運転を停止すべきであると考えたことはあるか」という質問に、酒井氏は「ありません」と言い切った。「何かしらの指示が出されれば止めて対策というのは、どこの国もしていない。運転中に評価をして対策を取るのがスタンダードだと今も思っている」と証言した。
しかし、運転継続しながら対策を取るのは、「一定の安全性が保障されていること」が前提だ。それは酒井氏自身も認めた。
耐震バックチェック(古い原発の安全性再確認)は2006年9月に開始され、揺れについての報告書(中間報告書)を、各電力会社が2008年3月に提出した。運転しながら確認作業は進められたが、旧来の想定を超えても、重要部分はすぐには壊れない余裕があることを電力会社はあらかじめ確かめていた。
ところが津波は違う。古い想定に余裕はなかった。新想定が数cm高く見直されるだけで、その想定津波のもとでは非常用発電機など最重要設備が動かなくなる。それなのに運転しながら対策を進めることは、リスク管理上とても許容されることではない。
事故の4日前、2011年3月7日、東電は保安院から津波対策を早急に進めるよう迫られていた。翌月には地震本部が貞観地震が再来する可能性について報告書を公開する手続きを進めており、地元自治体への説明も始めていた。
「地震本部が予測する貞観地震に、原発は耐えられるのか」と地元から問われた時、困った事態に陥る。東北電力は安全性をすでに確かめ、2010年にはこっそり報告書をまとめていた。ところが福島第一は非常用発電機や原子炉を冷やすポンプが動かなくなる。それが露見したら、運転継続は難しくなる。
もし、すぐには問題に気づかれなかったとしても、その先の見通しも暗かった。2016年までには津波対策を終える予定としていたが、その工法に目処は経っていなかったのだ。
そんな八方塞がりのもと、東電は漫然と福島第一の運転を続けて、事故の日を迎えた。
酒井氏は、福島第一を襲った大津波について「想定で考えているからといって、やっぱり来たかというより、びっくりしました」と述べた。
大津波の4年前、東電の柏崎刈羽原発が震度7の直下地震に襲われたばかりだった。酒井氏は、その原因になった活断層評価もとりまとめていた。
そして福島第一の津波である。これも自分が想定評価の責任者。自分が調査を担う東電の原発ばかりが、めったに起きないはずの地震に連続して襲われことは無かろうと、高をくくっていたのではないだろうか。





