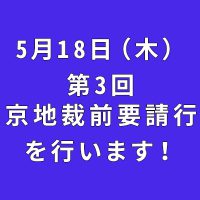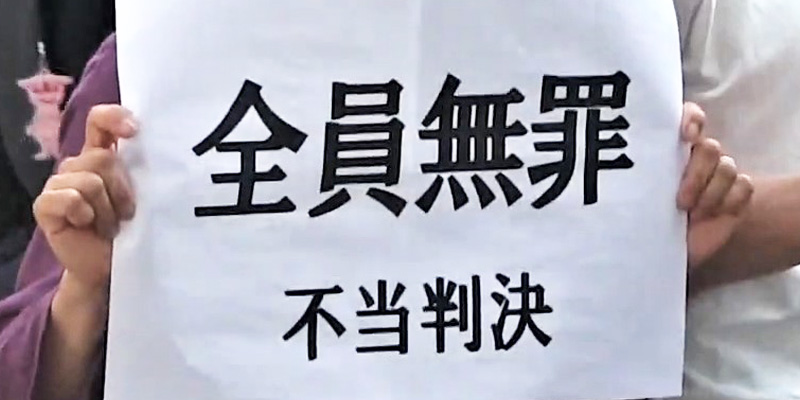
目次
東電刑事裁判(東京地裁平28刑(わ)374号、令1・9・19判決)
判決全文
*判例時報掲載の判決文より、伏字部分について裁判で明らかになっている部分は復元してあります。
【主文】
被告人らは、いずれも無罪。
【理由】
第1 本件公訴事実の要旨
本件公訴事実(平成30年5月23日付け訴因変更請求に基づく同年9月18日付け訴因変更後のもの。以下同じ。)の要旨は、「被告人勝俣恒久は、平成14年10月から東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)代表取締役社長、平成20年6月から同社代表取締役会長として、同社が福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22番地に設置した発電用原子力設備である福島第一原子力発電所(以下「本件発電所」という。)の運転、安全保全業務に従事していた者であり、被告人武黒一郎は、平成17年6月から同社常務取締役、原子力・立地本部本部長、平成19年6月から同社代表取締役副社長、同本部本部長、平成22年6月から同社フェローとして、被告人武藤栄は、平成17年6月から同社執行役員、同本部副本部長、平成20年6月から同社常務取締役、同本部副本部長、平成22年6月から同社代表取締役副社長、同本部本部長として、それぞれ被告人勝俣を補佐して、同発電所の運転、安全保全業務に従事していた者であるが、被告人3名は、いずれも上記各役職に就いている間、同発電所の原子力施設及びその付属設備等が想定される自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、防護措置等の適切な措置を講じるべき業務上の注意義務があったところ、同発電所に小名浜港工事基準面から10mの高さの敷地(以下、同基準面からの高さを「O.P.+10m」などといい、敷地の高さを「10m盤」などという。)を超える津波が襲来し、その津波が同発電所の非常用電源設備等があるタービン建屋等へ浸入することなどにより、同発電所の電源が失われ、非常用電源設備や冷却設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心に損傷を与え、ガス爆発等の事故が発生する可能性があることを予見できたのであるから、10m盤を超える津波の襲来によってタービン建屋等が浸水し、炉心損傷等によるガス爆発等の事故が発生することがないよう、防護措置等の適切な措置を講じることにより、これを未然に防止すべき業務上の注意義務があったのにこれを怠り、防護措置等の適切な措置を講じることなく、漫然と同発電所の運転を継続した過失により、平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震に起因して襲来した津波が、同発電所の10m盤上に設置されたタービン建屋等へ浸入したことなどにより、同発電所の全交流電源等が喪失し、非常用電源設備や冷却設備等の機能を喪失させ、これによる原子炉の炉心損傷等により、
1 同月12日午後3時36分頃、同発電所1号機原子炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起させ、同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、別紙被害者目録1≪略≫氏名欄記載の3名に、これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし、よって、その頃、それぞれ同所付近において、同目録1傷害の内容欄記載の傷害を負わせ、
2 同月14日午前11時1分頃、同発電所3号機原子炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起させ、同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、別紙被害者目録2≪略≫氏名欄記載の10名に、これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし、よって、その頃、それぞれ同所付近において、同目録2傷害の内容欄記載の傷害を負わせ、
3 別紙被害者目録3≪略≫氏名欄記載の43名を、上記水素ガス爆発等により、同目録3出発地欄記載の場所から、長時間の搬送や待機等を伴う避難を余儀なくさせた結果、それぞれ同目録3死亡日時欄記載の日時(年はいずれも平成23年である。)及び死亡場所欄記載の場所において、同目録3死因欄記載の死因により死亡させ、
4 上記水素ガス爆発等により、福島県双葉郡大熊町大字熊字新町176番地の1所在の医療法人博文会双葉病院の医師らが同病院から避難を余儀なくさせられた結果、同病院で入院加療中の別紙被害者目録4≪略≫氏名欄記載の1名に対する治療及び看護を不能とさせ、これにより同人を同目録4死亡日時欄記載の日時(年は平成23年である。)及び死亡場所欄記載の場所において、同目録4死因欄記載の死因により死亡させた。」というものである。
第2 前提となる事実
本件の主たる争点は、後記のとおり、本件発電所に一定以上の高さの津波が襲来することについての予見可能性の有無であるが、まずは、その前提となる事実関係について、認定、整理しておくこととする(以下、括弧内に証拠を引用する。)。
<判例時報により証拠の表示は省略ないし割愛>
1 東京電力による本件発電所の設置、運転
公訴事実記載の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)の発生当時、東京電力は、電気事業等の事業を営むことを目的とする株式会社であり、本件発電所を設置し、運転していた。
本件地震発生当時、東京電力においては、原子力・立地本部が、本件発電所の運転・安全保全業務を統轄し、同本部内の原子力設備管理部が、原子力発電設備の中・長期的課題の集約・検討、長期保全計画の策定、土木・建築・電気・機械設備管理の取りまとめ、技術検討、耐震設計に関する検討、取りまとめ等の業務を分掌していた。このうち本件発電所における津波水位評価の業務は、組織変更等により順次、平成11年12月以降は原子力技術部土木調査グループ、平成16年6月以降は原子力技術・品質安全部土木グループ、平成19年4月以降は原子力設備管理部土木技術グループ、同年11月以降は同部新潟県中越沖地震対策センター土木グループ、平成20年7月以降は同センター土木調査グループ、平成23年2月以降は同部原子力耐震技術センター土木調査グループが分掌していた(以下、これらのグループを組織変更の前後を通じて「土木グループ」という。)。
2 被告人らの東京電力における地位と権限等
(1) 被告人勝俣
被告人勝俣は、平成14年10月から平成20年6月まで代表取締役社長を務め、取締役会を組織し、会社を代表し、取締役会の決議に基づき、会社業務の執行を統轄する権限を有していた。また、平成20年6月から本件地震発生時まで代表取締役会長を務め、取締役会を組織し、株主総会及び取締役会を招集し、その議長となる権限や、常務会の構成員となり、議案提案権を有する権限を有していた。
(2) 被告人武黒
被告人武黒は、平成17年6月から平成19年6月まで常務取締役、原子力・立地本部本部長を務め、常務取締役として、取締役会を組織し、社長を補佐し、所管する業務における権限を社長から配分されて会社業務を執行する権限を有するとともに、同本部本部長として、同本部に所属する各部長の総括、必要に応じた適切な指示・指導及び所属する各部が受け持つ諸業務の円滑な推進に向けた本部内の総合調整を行い、原子力発電所等の事業活動を円滑に進めるための相互調整、原子力発電所長等に対する必要に応じた適切な指示・指導を行うなどの権限を有していた。また、平成19年6月から平成22年6月まで代表取締役副社長、同本部本部長を務め、代表取締役副社長として、取締役会を組織し、会社を代表し、社長を補佐し、会社業務を執行するなどの権限を有するとともに、上記の原子力・立地本部本部長としての権限を有していた。さらに、平成22年6月から本件地震発生時までフェローを務め、技術系の最高幹部として社長を直接補佐し、社内活動面では、技術政策策定への参画と高度技術の経営への迅速な反映、専門分野・関係分野における技術の審査・研究等に対する指導・助言等の役割を担っていたが、取締役会及び常務会の構成員ではなく、会社業務を執行する権限を有しなかった。
(3) 被告人武藤
被告人武藤は、平成17年6月から平成20年6月まで執行役員、原子力・立地本部副本部長を務め、技術系の事務についての相談に応じるなどして同本部に所属する各部の部長を指導し本部長を補佐するなどの職務を遂行していた。また、平成20年6月から平成22年6月まで常務取締役、同本部副本部長を務め、前記の常務取締役としての権限を有するとともに、上記の同本部副本部長としての職務を遂行していた。さらに、平成22年6月から本件地震発生時まで代表取締役副社長、同本部本部長を務め、前記の代表取締役副社長としての権限を有するとともに、前記の同本部本部長としての権限を有していた。
3 本件発電所の概要
(1) 配置、構造
本件発電所は、福島県双葉郡大熊町及び同郡双葉町にまたがって位置し、その敷地は、東側が太平洋に面し、海岸線に長軸を持つ半楕円状の形状となっていた。本件発電所には、1号機から6号機まで6基の沸騰水型軽水炉が設置されており、その配置は別紙1のとおり、北側から順次、敷地北部の同郡双葉町側に6号機及び5号機が、敷地南部の同郡大熊町側に1号機から4号機までが配置され、6号機から4号機までの敷地全体の東側の海岸には防波堤が各号機の前面を取り囲むように三角形の二辺の形状で設置されていた。各号機は、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋及びサービス建屋等から構成されており、これら建屋の一部については、隣接プラントと共用となっていた。このうち1号機から4号機までの各建屋の配置は別紙2のとおりであり、原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、サービス建屋及び運用補助共用施設等の主要建屋が10m盤に配置され、非常用海水系ポンプが海側の4m盤の屋外に配置されていた。なお、5号機及び6号機の主要建屋は13m盤に配置されていた。
(2) 1号機から3号機までの安全機能
沸騰水型軽水炉は、原子炉の中でウラン燃料が核分裂する際に発生する熱で蒸気を作り、その蒸気でタービンを回し、タービンに連結されている発電機を回して発電し、タービンを回し終わった蒸気を復水器の中で配管内を流れている海水によって冷やし、再び原子炉の中に戻すという仕組みになっている。原子炉内には、人体に悪影響を及ぼすおそれのある放射線を放出する放射性物質が多量に存在しており、かかる物質の原子炉施設外への漏出を防止するために、原子炉施設には、異常を検出して原子炉を速やかに停止する機能(止める機能)、原子炉停止後も放射性物質の崩壊により発熱を続ける燃料の損傷を防止するための、炉心の冷却を続ける機能(冷やす機能)、燃料から放出された放射性物質の施設外への漏えいを抑制する機能(閉じ込める機能)が備え付けられている。
本件発電所の1号機から3号機までにおいても、まず、原子炉を「止める機能」を担うものとして、燃料集合体と燃料集合体の間に、核分裂によって生じた中性子を吸収する物質で作られた制御棒を挿入する設備や、その設備が作動しない場合に備えて、中性子吸収能力の高い五ほう酸ナトリウム溶液を圧力容器内に注入する設備が備え付けられていた。次に、炉心を「冷やす機能」を担うものとして、非常時に炉心を冷やす設備、炉心を冷やす用途以外のために作られたラインを非常時に代替利用して圧力容器内等に水を注水することによって炉心を冷やす代替注水設備及び平常時から圧力容器内に水を注水しているラインを非常時に利用して圧力容器内に水を注水することによって炉心を冷やす通常注水設備が備え付けられていた。さらに、放射性物質を「閉じ込める機能」を担うものとして、①ウラン燃料を焼き固めたペレット、②ペレットをジルコニウム合金で覆った燃料被覆管、③鋼鉄製の原子炉圧力容器、④同じく鋼鉄製の原子炉格納容器(ドライウェルと圧力抑制室から構成される。)及び⑤コンクリート造りの原子炉建屋という五重の障壁が備え付けられていた。
このうち「冷やす機能」を担う設備は、2号機及び3号機の非常時に炉心を冷やす設備である原子炉隔離時冷却系(RCIC)が電動駆動の弁を手動で開くことによって作動させることができるほかは、いずれも制御電源や駆動電源等として直流電源と交流電源の双方又は一方が必要であった。
(3) 1号機から3号機までの電源設備
本件発電所の1号機から3号機までの原子炉施設では、運転中は、各号機の発電機で発電した電気から交流の電力の供給を受け、原子炉が停止した場合、本件発電所の外部にある新福島変電所から送電される交流の電力又は運転中の隣接号機の主発電機から供給される交流の電力の供給を受けこれらの電力の供給も受けられなくなった場合、各号機に設置されている2台の非常用ディーゼル発電機が起動し、同発電機から非常用の電源盤を経由して交流の電力の供給を受ける設計となっていた。そして、各原子炉施設に供給された交流の電力は、交流の電力を必要とする機器に供給されるほか、電源盤を経由して、充電器で直流の電力に変換されて、蓄電池に充電されるとともに、直流の電力を必要とする機器に供給され、交流の電力の供給を受けられなくなった場合、蓄電池から電源盤を経由して直流の電力の供給を受ける設計となっていた。
このうち非常用ディーゼル発電機は、1号機及び3号機ではタービン建屋地下1階に海水冷却式のもの各2台が、2号機ではタービン建屋地下1階に海水冷却式のもの1台及び運用補助共用施設1階に空気冷却式のもの1台がそれぞれ設置されており、これらの海水冷却式の非常用ディーゼル発電機を作動させるためには、海水系ポンプを作動させる必要があった。また、電源盤は、1号機から3号機まででは各号機のタービン建屋又はコントロール建屋の地下1階等に設置されていた。
4 本件事故の概要
(1) 本件地震の発生と津波の襲来
平成23年3月11日(以下、年月日については適宜表記を省略することがある。)午後2時46分、三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近、深さ約24kmの地点、本件発電所からの震央距離約178m、震源距離約180km)を震源とする、震源の物理的な規模を表す地震モーメントから決められる地震の大きさの指標であるモーメントマグニチュードMw9.0の「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(本件地震)が発生した。この地震は、陸のプレートとその下に沈み込む太平洋プレートの境界で発生した、西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型地震であった。複数の領域が震源域として連動しており、震源域は、日本海溝の海溝軸西側の岩手県沖から茨城県沖までに及んでおり、その長さは400km以上、幅は約200kmで、断層のすべり量は最大50m以上であったと推定されており、地震の規模、震源域とも、国内観測史上最大のものであった。
本件地震に伴い津波が発生し、その第1波(押し波のピーク)が午後3時27分頃、第2波(2段目の押し波のピーク)が午後3時36分から37分までの間頃、それぞれ本件発電所の敷地に到達した。第2波は、発電所護岸における津波の高さ(平常潮位から津波によって海面が上昇した高さの差)が約13mであり、防波堤を越えて、全面的に本件発電所の敷地へ遡上し、4m盤及び10m盤の全域が浸水した。10m盤における浸水高(建物や設備に残された変色部や漂着物等の痕跡の基準面からの高さ)は概ねO.P.+約11.5mないし+約15.5m、浸水深(地表面すなわち敷地面からの高さ)は概ね約1.5mないし約5.5mであった。
(2) 本件地震発生から津波到達までの1号機から4号機までの状況
本件地震発生時、本件発電所の1号機から3号機までは、定格出力運転中であった。4号機は、定期検査のため停止中であり、全燃料が原子炉圧力容器から取り出されて原子炉建屋内の使用済み燃料プールに貯蔵されており、新福島変電所から送電される交流の電力の供給を受けていた。1号機から3号機まででは、本件地震の震動を検知したことから、午後2時47分頃、原子炉の炉心に全ての制御棒が全挿入されて原子炉が緊急停止し、各号機及び隣接号機の主発電機で発電した電気から交流の電力の供給を受けられなくなった。
このうち1号機では、地震の震動により、新福島変電所から送電されてくる交流の電力の受電設備である遮断器が作動して同電力の供給を受けられなくなっていたため、午後2時48分頃、2台の非常用ディーゼル発電機が自動で起動し、同発電機からの電力の供給が開始した。そして、午後2時52分頃から午後3時30分過ぎ頃までの間、非常時に炉心を冷やす設備である非常用復水器(IC)が間断的に、午後3時5分頃以降、同じく非常時に炉心を冷やす設備である格納容器冷却系(CCS)の圧力抑制室冷却モードがそれぞれ作動していた。2号機及び3号機では、原子炉の緊急停止後、新福島変電所から送電される交流の電力に切り替わったが、地震の震動により、受電設備等に異常が生じて同電力の供給を受けられなくなったため、午後2時48分頃、各2台の非常用ディーゼル発電機が自動で起動し、同発電機からの電力の供給が開始した。2号機では、午後2時50分頃以降、非常時に炉心を冷やす設備である原子炉隔離時冷却系(RCIC)が間断的に、午後3時頃以降、同じく非常時に炉心を冷やす設備である残留熱除去系(RHR)の圧力抑制室冷却モードがそれぞれ作動していた。3号機では、午後3時6分頃から午後3時25分頃までの間、原子炉隔離時冷却系(RCIC)が作動した。なお、4号機では、もともと新福島変電所から送電される交流の電力の供給を受けていたが、2号機及び3号機と同様にこの交流の電力の供給を受けられなくなったため、運用補助共用施設1階に設置されていた空気冷却式非常用ディーゼル発電機1台が自動で起動し、同発電機からの電力の供給が開始した。
(3) 津波到達後の1号機から4号機までの状況
本件地震に伴う津波の到達後、1号機から4号機まででは、海水系ポンプがモーターの冠水により作動不能となった。また、タービン建屋の地上開口部等から建屋内に大量の水が浸入したことにより、タービン建屋地下1階に設置されていた海水冷却式非常用ディーゼル発電機が、本体の被水により作動不能となった。運用補助共用施設1階に設置されていた2号機及び4号機の空気冷却式非常用ディーゼル発電機各1台は、いずれも本体の被水を免れたものの、同施設地下1階に設置されていた同発電機で発電された電気を中継する電源盤の被水により、同発電機に停止信号が発信され、午後3時40分頃までに停止した。さらに、上記のとおり大量の水が浸入したことにより、タービン建屋1階、地下1階、運用補助共用施設地下1階又はコントロール建屋地下1階等に設置された電源盤又は蓄電池の多くが被水し、電源盤から電力を供給することができなくなるとともに、非常用ディーゼル発電機に停止信号が発信された。このようにして、1号機から4号機まででは、午後3時40分頃までに、全ての非常用ディーゼル発電機が停止し、全ての交流電源を喪失した。また、1号機と2号機では、午後3時50分頃にほとんどの直流電源を喪失し、3号機では、蓄電池からの直流電源が確保されていたが、交流電源の喪失により蓄電池への充電機能が失われていた。1号機では、海水系ポンプの作動不能又は全ての交流電源若しくはほとんどの直流電源の喪失により、格納容器冷却系(CCS)の圧力抑制室冷却モードの作動が停止し、その他の炉心を「冷やす機能」を担う設備を作動させることができず、又は作動させることができてもほとんど機能しない状態にあって、炉心を「冷やす機能」を喪失した。その結果、3月11日午後3時30分過ぎ以降、圧力容器内にほとんど注水が行われなかったことにより、翌12日午前4時頃以降、断続的に消防車を用いた圧力容器内への注水が行われたものの、圧力容器内の水位が低下して燃料が圧力容器内の気体部分に露出する状態(炉心露出の状態)になっており、崩壊熱により燃料及び被覆管の温度が急上昇し、被覆管の材料のジルコニウムが圧力容器内の水蒸気と化学反応(水-ジルコニウム反応)を起こして大量の水素ガスが発生するとともに、被覆管の溶融により燃料から多量の放射性物質が放出され、これらが圧力容器のいずれかの場所から格納容器内に、格納容器内のいずれかの場所から原子炉建屋内にそれぞれ漏えいし、蓄積した。そして、何らかの原因で原子炉建屋内の水素ガスに着火し、12日午後3時36分頃に原子炉建屋が爆発し、これらの過程で放射性物質が大気に放出された。
2号機では、津波到達直後から遅くとも同月14日午後1時頃までの間、原子炉隔離時冷却系(RCIC)が作動していたほかは、海水系ポンプの作動不能又は全ての交流電源若しくはほとんどの直流電源の喪失により、炉心を「冷やす機能」を担う設備を作動させることができず、又は作動させることができてもほとんど機能しない状態にあって、炉心を「冷やす機能」を喪失した。その結果、遅くとも同日午後1時頃以降、圧力容器内への注水が行われなかったことにより、同日午後7時54分頃以降、断続的に消防車を用いた圧力容器内への注水が行われたものの、1号機と同様の経過を経て、圧力容器内で、大量の水素ガスが発生するとともに、多量の放射性物質が放出され、これらが圧力容器のいずれかの場所から格納容器内に漏えいし、格納容器内のいずれかの場所から原子炉建屋内に漏えいした。そして、前記のとおり1号機の原子炉建屋が爆発した際の衝撃により、2号機の原子炉建屋上部のブローアウトパネルが外れて隙間ができ、この隙間からの漏出等により、水素ガス及び放射性物質が大気に放出された。
3号機では、同月11日午後4時3分頃から翌12日午前11時36分頃まで原子炉隔離時冷却系(RCIC)が、12日午後0時35分頃から翌13日午前2時42分頃まで非常時に炉心を冷やす設備である高圧注水系(HPCI)がそれぞれ作動したが、いずれも蓄電池の電気の残量不足により作動を再開できなくなった。そのほかの炉心を「冷やす機能」を担う設備についても、海水系ポンプの作動不能又は全ての交流電源の喪失により作動させることができず、炉心を「冷やす機能」の多くを喪失した。その結果、13日午前2時42分頃以降、圧力容器内に注水が行われなかったことにより、同日午前5時8分頃から午前9時25分頃まで、代替注水設備であるディーゼル駆動消火ポンプ(D/DFP)を用いた消火系(FP)によって、圧力抑制室、ドライウェル又は圧力容器内への注水が行われ、同日午前9時25分頃以降は消防車を用いた圧力容器内への注水が行われたものの、1号機と同様の経過を経て、圧力容器内で大量の水素ガスが発生するとともに、多量の放射性物質が放出され、これらが圧力容器のいずれかの場所から格納容器内に、格納容器内のいずれかの場所から原子炉建屋内にそれぞれ漏えいし、蓄積した。そして、何らかの原因で原子炉建屋内の水素ガスに着火し、14日午前11時1分頃に原子炉建屋が爆発し、これらの過程で放射性物質が大気に放出された。
4号機では、3号機の格納容器を減圧するため、13日午前9時頃以降、格納容器内の気体を排気筒から大気へ放出する操作(格納容器ベント)を行った際、3号機で発生していた大量の水素ガスの一部が、3号機と4号機をつなぐ配管を通じて4号機の原子炉建屋内に流れ込んで蓄積し、何らかの原因で原子炉建屋内の水素ガスに着火し、15日午前6時14分頃に原子炉建屋が爆発した。
(4) 死傷結果の発生
ア 公訴事実1の傷害結果の発生
別紙被害者目録1≪略≫氏名欄記載の3名は、本件発電所1号機の注水作業に従事していた者であるが、3月12日午後3時36分頃、消防車に乗って2号機と3号機の各原子炉建屋の間の道路を走行し、又は1号機若しくは2号機のタービン建屋東側にいたところ、1号機の原子炉建屋が水素ガス爆発し、爆発により飛び散ったがれきに接触し、又は爆風で飛ばされて体を地面に打ちつけたことにより、同目録1傷害の内容欄記載の傷害を負った。
イ 公訴事実2の傷害結果の発生
別紙被害者目録2≪略≫氏名欄記載の10名は、本件発電所における事故収束のための作業に従事していた者であるが、同月14日午前11時1分頃、2号機又は3号機のタービン建屋東側等で給水ホースの敷設作業などをしていたところ、3号機原子炉建屋が水素ガス爆発し、爆発により飛び散ったがれきに接触し、又はがれきを避けるために走って避難した際に転倒したことにより、同目録2傷害の内容欄記載の傷害を負った。
ウ 公訴事実3の死亡結果の発生
前記の原子炉建屋の爆発等により多量の放射性物質が大気に放出された。本件発電所事故に係る原子力災害対策本部長は、福島県知事、大熊町長及び双葉町長等の地方公共団体の長に対し、原子力災害対策特別措置法20条3項の規定に基づき、順次、①3月11日午後9時23分、本件発電所から半径3キロメートル圏内の居住者等の立退き、半径10キロメートル圏内の居住者等の屋内退避、②12日午前5時44分、本件発電所から半径10キロメートル圏内の居住者等の立退き、③同日午後6時25分、本件発電所から半径20キロメートル圏内の居住者等の立退き、④15日午前11時、本件発電所から半径20キロメートル圏内の居住者等の立退き、半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の居住者等の屋内退避について、それぞれ対象区域内の居住者等に対するその旨の周知を指示した。福島県双葉郡大熊町大字熊字新町176番地の1所在の医療法人博文会双葉病院(以下「双葉病院」という。)は、本件発電所の南西約4.5kmに、同町大字熊字新町369番地の1所在の同法人介護老人保健施設ドーヴィル双葉(以下「ドーヴィル双葉」という。)は、本件発電所の南西約4.4kmにそれぞれ位置している。本件地震発生当時、双葉病院には、外泊中の2名を除く338名の患者が入院しており、寝たきりの患者や自力で歩行できない患者が多く含まれていた。ドーヴィル双葉には、98名が入所しており、いずれも病状が安定し、介護を必要としていたが、医療行為はほぼ必要のない状態であった。
双葉病院の入院患者のうち209名は、同月12日午後2時頃までに、バスに乗って避難先へ出発した。双葉病院のその余の患者129名及びドーヴィル双葉の入所者98名は取り残されたままであった。
陸上自衛隊第12旅団輸送支援隊が、同月14日午前4時頃、ドーヴィル双葉及び双葉病院に到着し、同日午前7時頃から午前10時30分頃までの間に、別紙被害者目録3≪略≫番号1から18まで、20、30、32、42及び43の氏名欄記載の23名を含むドーヴィル双葉の入所者98名全員と双葉病院の入院患者30数名をバスに乗せて避難先へ出発した。これらの患者及び入所者は、バスに乗せられて、福島県南相馬市所在の相双保健所、福島市内、同県いわき市所在のいわき光洋高等学校、同市所在のいわき開成病院を経由して、同日午後9時35分頃、いわき光洋高等学校に再度到着し、同校体育館に搬送された。上記23名は、長時間にわたる搬送及び待機等を伴う避難を余儀なくされた結果、身体に過度の負担がかかり、同目録3死亡日時欄記載の日時に、上記の搬送の過程又はそれぞれの最終的な搬送先である同目録3死亡場所欄記載の場所において、同目録3死因欄記載の死因により死亡した。
自衛隊統合任務部隊搬送部隊及び陸上自衛隊第12旅団衛生隊が、同月15日午前9時頃以降、双葉病院に到着し、午後0時15分頃までに、別紙被害者目録3≪略≫番号19、21、22、31、34から38まで、40及び41の氏名欄記載の11名を含む双葉病院の入院患者54名をバス等に乗せて避難先へ出発した。これらの患者は、途中で、別のバスに乗せ換えられて、途中で別の搬送先に搬送される者もありつつ、福島県田村市所在の田村市総合体育館、同県二本松市所在の福島県男女共生センター、福島市所在の福島県庁前を経由して、16日午前1時頃、福島県伊達市所在の伊達ふれあいセンターに到着し、同所に搬送された。上記11名は、長時間にわたる搬送及び待機等を伴う避難を余儀なくされた結果、身体に過度の負担がかかり、同目録3死亡日時欄記載の日時に、それぞれの最終的な搬送先である同目録3死亡場所欄記載の場所において、同目録3死因欄記載の死因により死亡した。
陸上自衛隊第12旅団混成部隊が、同月16日午前0時頃以降、双葉病院に到着し、午前3時40分頃までに、別紙被害者目録3≪略≫番号23から29まで、33及び39の氏名欄記載の9名を含む双葉病院の入院患者35名をバス等に乗せて避難先へ出発した。これらの患者は、途中で、別のバスに乗せ換えられて、途中で別の搬送先に搬送される者もありつつ、福島県男女共生センター、福島県二本松市所在の県立霞ヶ城公園駐車場を経由して、同日、福島市所在のあづま総合運動公園に到着し、同所の施設内に搬送された。上記9名は、長時間にわたる搬送及び待機等を伴う避難を余儀なくされた結果、身体に過度の負担がかかり、同目録3死亡日時欄記載の日時に、上記の搬送の過程又はそれぞれの最終的な搬送先である同目録3死亡場所欄記載の場所において、同目録3死因欄記載の死因により死亡した。
エ 公訴事実4の死亡結果の発生
双葉病院では、同月14日午前10時30分頃までに多くの病院職員と入院患者が避難した後、同病院院長鈴木市郎及び同病院医師神保博州が、病院に残された患者らの診察や治療に当たっていた。両名の医師は、同日午後10時30分頃、警察官から直ちに一時避難するよう命じられ、警察車両に乗せられて双葉病院を後にしたが、その後同病院へ戻ることを許されず、翌15日昼頃、患者らが既に救助されていわき開成病院等にいる旨を聞くや、直ちにいわき開成病院へ向かった。
別紙被害者目録4≪略≫氏名欄記載の1名は、双葉病院に入院していたが、上記のとおり医師らが同病院からの避難を余儀なくさせられた結果、必要な治療及び看護を受けられなくなったことにより、同月15日頃、双葉病院において、同目録4死因欄記載の死因により死亡した。
(5) 以下においては、本件地震の発生から本件被害者らの死傷結果の発生までの一連の事象を「本件事故」ということとする。
第3 本件の主たる争点
1 はじめに
過失により人を死傷させたとして業務上過失致死傷罪が成立するためには、人の死傷の結果の回避に向けた注意義務、すなわち結果回避義務を課す前提として、人の死傷の結果及びその結果に至る因果の経過の基本的部分について予見可能性があったと合理的な疑いを超えて認められることが必要である。
2 当事者の主張の骨子
予見可能性についての指定弁護士及び弁護人らの各主張の骨子は以下のとおりである。
(1) 指定弁護士の主張
本件において前記の予見可能性があったというためには、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来することを予見できたことが必要である。その予見は、もとより一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りないが、上記のような津波が襲来する可能性が相応の根拠をもって示されていれば、予見可能性を認めることができる。そして、被告人らは、以下のアからコまでの事実などを重要な契機として、一定の情報収集義務(情報補充義務)を尽くしていれば、上記の予見は可能であった。
ア 平成14年7月31日、文部科学省地震調査研究推進本部(以下「地震本部」という。「推本」とも呼ばれていた。)による「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」という。)の公表
イ 平成18年9月19日、原子力安全委員会による「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂
ウ これを受けた原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)による「耐震バックチェック」の指示
エ 平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震を契機に、東京電力において継続的に開催されることとなった「中越沖地震対応打合せ」における議論
オ とりわけ、平成20年2月16日開催の「中越沖地震対応打合せ」における山下和彦中越沖地震対策センター長の報告
カ 「長期評価」に基づく東電設計株式会社(以下「東電設計」という。)によるパラメータスタディの実施
キ 平成20年6月10日及び同年7月31日の吉田昌郎原子力設備管理部長、山下対策センター長らによる被告人武藤に対する東電設計の行った津波水位解析に関する報告
ク 平成21年2月11日開催の「中越沖地震対応打合せ」での吉田部長の発言
ケ 平成21年4月ないし5月頃の吉田部長らによる被告人武黒に対する東電設計の行った津波水位解析に関する報告
コ 土木学会第4期津波評価部会における議論
そして、被告人らは、10m盤を超える津波が襲来することを予見できたのであるから、10m盤を超える津波の襲来によってタービン建屋等が浸水し、炉心損傷等によるガス爆発等の事故が発生することのないよう、結果回避のための適切な措置を講じることにより、これを未然に防止すべきであった。ここに結果回避のための適切な措置とは、①津波が敷地に遡上するのを未然に防止する対策、②津波の遡上があったとしても、建屋内への浸水を防止する対策、③建屋内に津波が浸入しても、重要機器が設置されている部屋への浸入を防ぐ対策、④原子炉への注水や冷却のための代替機器を津波による浸水のおそれがない高台に準備する対策、以上全ての措置を予め講じておくことであり、⑤これら全ての措置を講じるまでは運転停止措置を講じることである。そして、⑤の運転停止措置を講じることを前提に、被告人らは、遅くとも平成23年3月初旬には、上記の予見が可能であった。
(2) 弁護人らの主張
本件において前記の予見可能性があったというためには、単に10m盤を超える津波の襲来を予見できただけでは足りず、本件発電所に10m盤及び13m盤を大きく超える津波が敷地の東側正面全面から襲来することを予見できたことが必要である。指定弁護士の主張する結果回避措置を法的に義務付けるには、一般的・抽象的な危惧感ないし不安感では足りないのはもちろん、信頼性及び成熟性の認められる知見に基づく具体的根拠を伴う予見可能性が必要である。「長期評価」は、具体的根拠を示しておらず、結果回避措置を義務付けるに足りる信頼性及び成熟性はなく、東電設計による計算結果どおりの津波が襲来することの予見可能性を生じさせるものではなかった。
3 本件の主たる争点
以上のとおり、本件の主たる争点は、被告人らにおいて、本件発電所に一定以上の高さの津波が襲来することについての予見可能性があったと認められるか否かであり、その前提として、どのような津波を予見すべきであったのか、そして、津波が襲来する可能性について、どの程度の信頼性、具体性のある根拠を伴っていれば予見可能性を肯認してよいのかという点に争いがある。
第4 本件における予見可能性についての考え方
1 予見すべき津波
業務上過失致死傷罪が成立するためには、行為者の立場に相当する一般人を行為当時の状況に置いたときに、行為者の認識した事情を前提に、前記のとおり、人の死傷の結果及びその結果に至る因果の経過の基本的部分について予見可能性があったと認められることが必要である。
前記認定のとおり、本件発電所においては、本件地震発生直後に1号機から3号機までの原子炉が緊急停止して原子炉を「止める機能」は働いたものの、地震の震動により本件発電所の外部からの電力の供給を受けられなくなった後、10m盤を超える津波が襲来して10m盤に配置されたタービン建屋、コントロール建屋、運用補助共用施設等の主要建屋へ浸入し、建屋内部に設置された非常用の電源設備等の多くが被水したことにより、電源が失われて炉心を「冷やす機能」を喪失し、炉心が溶融し、水素ガス爆発等が惹起されて人の死傷の結果が生じるに至ったものである。このように、本件事故においては、10m盤を超える津波が襲来して10m盤上のタービン建屋等へ浸入したことが本件事故の発生に大きく寄与したことが明らかであるから、10m盤を超える津波の襲来が、人の死傷の結果に至る因果の経過の根幹部分をなしているというべきである。そして、そのような津波が襲来することの予見可能性があれば、津波が本件発電所の主要建屋に浸入し、非常用電源設備等が被水し、電源が失われて炉心を「冷やす機能」を喪失し、その結果として人の死傷を生じさせ得るという因果の流れの基本的部分についても十分に予見可能であったということができる。したがって、本件公訴事実に係る業務上過失致死傷罪が成立するためには、被告人らにおいて、10m盤を超える津波が襲来することの予見可能性が必要であるが、弁護人らの主張のように、本件事故において現に発生した10m盤における浸水高O.P.+約11.5mないし+約15.5mの津波、又は10m盤若しくは13m盤を大きく超える津波が東側正面全面から襲来することの予見可能性までは不要というべきである。
2 津波襲来の可能性の根拠の信頼性、具体性について
(1) はじめに
この点、前記のとおり、指定弁護士は、津波襲来の可能性が相応の根拠をもって示されていれば予見可能性を認めることができる旨主張し、他方、弁護人らは、信頼性及び成熟性の認められる知見に基づく具体的根拠を伴う予見可能性が必要である旨主張している。
この点については、個々の具体的な事実関係に応じ、問われている結果回避義務との関係で相対的に、言い換えれば、問題となっている結果回避措置を刑罰をもって法的に義務付けるのに相応しい予見可能性として、どのようなものを必要と考えるべきかという観点から、判断するのが相当であると解される。
そこで、次においては、本件結果を回避するために、どのような措置を講じるべきであったか、これを踏まえて本件における結果回避義務の内容、性質等について順次検討することとする。
(2) 結果回避のための防護措置等
本件結果を回避するために必要な措置について、指定弁護士は、前記のとおり、①津波が敷地に遡上するのを未然に防止する対策、②津波の遡上があったとしても、建屋内への浸水を防止する対策、③建屋内に津波が浸入しても、重要機器が設置されている部屋への浸入を防ぐ対策、④原子炉への注水や冷却のための代替機器を津波による浸水のおそれがない高台に準備する対策、以上全ての措置を予め講じておくことであり、⑤これら全ての措置を講じるまでは運転停止措置を講じることであるとした上で、①から④までの全ての措置を予め講じておけば、本件事故を回避することができた旨主張する。
しかしながら、指定弁護士の主張を前提としても、いつの時点までに前記①から④までの措置に着手していれば、本件事故前までにこれら全ての措置を完了することができたのか、判然とせず、前記のとおり、10m盤を超える津波襲来の予見可能性が必要であったと考えた場合、そのような津波襲来の可能性に関する情報に被告人らが接するのは、後記のとおり、被告人武藤が早くて平成20年6月10日、被告人武黒が早くて被告人武藤から報告を受けた同年8月上旬、被告人勝俣が早くて平成21年2月11日と認められるところ、仮にこれらの時期から本件発電所において前記①から④までの全ての措置を講じることに着手していたとしても、本件事故発生前までにこれら全ての措置を完了することができたのか、証拠上も明らかではない。現に、指定弁護士も、被告人らが、上記の各時期に、前記①から④までの措置を講じることに着手していれば、これを完了することができ、これにより本件事故を回避し得たとの主張はしていない(公判前整理手続における平成28年8月9日付け釈明書)。
そうすると、結局のところ、本件事故を回避するためには、本件発電所の運転停止措置を講じるほかなかったということになる。そして、運転停止措置を講じるべきであった時点について、指定弁護士は、原子炉停止後の燃料の崩壊熱の発生量等を踏まえ、遅くとも平成23年3月初旬(より具体的には3月6日)までに運転停止措置を講じていれば、本件事故を回避することができた旨主張している。したがって、本件において問題となっている結果回避義務は、平成23年3月初旬までに本件発電所の運転停止措置を講じること、これに尽きていることとなる。
(3) 検討の視点
ところで、原子炉内には前記のとおり人体に悪影響を及ぼすおそれのある放射線を放出する放射性物質が多量に存在しており、原子力発電所で事故が発生すれば、放射性物質が施設外へ漏えいし、施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、甚大な被害をもたらすおそれがあることは、公知の事実といってよい。実際、本件事故の結果として公訴事実に掲げられているのは、合計44名の死亡、合計13名の傷害というものである上、そのような結果が生じる過程では多量の放射性物質が環境に放出されて、深刻な事態が生じているのであって、その結果が誠に重大であることは明らかである。すなわち、本件で問題となっているのは、このような重大な結果の発生を回避するための結果回避義務であるということを、まずもって考慮する必要がある。
しかしながら、他方において、東京電力は、電気事業法に基づいて電力の供給義務を負っているところ(同法18条)、現代社会における電力は、一定の地域社会における社会生活や経済活動等を支えるライフラインの一つであって、本件発電所はその一部を構成しており、本件発電所の運転には小さくない社会的な有用性が認められ、その運転停止措置を講じることとなれば、ライフライン、ひいては当該地域社会にも一定の影響を与えるということについても考慮すべきである。また、本件で問題となっている結果回避義務は、本件発電所の運転停止という作為義務を内容とするものであるから、その作為がどのような負担、困難等を伴うものであるのかについても、作為義務を課す前提となる作為の容易性又は困難性という観点から、考慮して然るべきと考えられる。
本件で問題となっている結果回避義務の内容、性質等に関して考慮すべきは、主として以上のとおりであって、そのような結果回避措置を法的に義務付けるに相応しい予見可能性をどのようなものと考えるべきかを検討することになる。上記のような結果の重大性を強調するあまり、その発生メカニズムの全容解明が今なお困難で、正確な予知、予測に限界のある津波という自然現象について、想定し得るあらゆる可能性を、その根拠の信頼性や具体性の程度を問わずに考慮して必要な措置を講じることが義務付けられるとすれば、法令上、原子力発電所の設置、運転が認められているにもかかわらず、原子力発電所の運転はおよそ不可能ということとなり、原子力発電所の設置、運転に携わる者に不可能を強いる結果となるのであって、もとより指定弁護士の主張もそのような前提に立つものとは思われない。前記のような津波襲来の可能性があるとする根拠の信頼性、具体性の程度については、結局のところ、上記のような本件における結果回避義務の内容、性質等を踏まえ、原子炉の安全性についての当時の社会通念を中心として、平成23年3月初旬の時点までにおいて、どのような知見があり、本件発電所の安全対策としてどのような取組が行われ、本件発電所がどのような施設として運用されてきたのかなども考慮した上で、これを決するほかないというべきである。そして、上記の社会通念は、法令上の規制やそれを補完する国の安全対策における指針、審査基準等に反映されていると考えるほかないのであるから、そのような法令上の規制やそれを補完する指針、審査基準等において、原子炉の安全性確保がどのように考えられていたのかを検討していくことになる。
そこで、以下においては、平成23年3月初旬の時点までにおいて、①地震及び津波に関し、どのような知見があり、その知見に対する評価、受け止めがどのようなものであったか、②原子炉安全対策に関して、どのような法令上の規制がされ、それを受けて国においてどのような規制、審査等が行われてきたか、③そのような中で、東京電力が、原子炉安全対策にどのように取り組み、対応してきたのかなどについて、指定弁護士が予見可能性の前提となる「重要な契機」として主張している事実関係を中心に概観し、さらに、本件発電所の運転停止措置に伴う負担等についてもみていくこととする。
第5 予見可能性判断の前提となる事実関係
1 平成23年3月初旬の時点における地震及び津波に関する一般的知見
(1) 地震について
地震とは、断層が急激にすべって地震波が発生し、それが地球内部を伝播して地面を揺らす現象である。日本列島付近で起こる地震には、活断層による地震、プレート境界の地震及びプレート内部の地震がある。このうちプレート境界の地震は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むときに、固着している大陸プレートを一緒に引きずり込み、この引きずり込みがある限界に達したときに、両プレートの境界面が破壊されてずれ、海洋プレートが沈み、大陸プレートが跳ね上がることによって発生する。プレート内部の地震は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むときに曲げられる結果、海洋プレート内で岩盤がずれることによって発生する。三陸沖北部から房総沖にかけての領域では、太平洋プレートが年約8ないし9cmの速さで陸のプレートの下に沈み込んで日本海溝が造られている。プレートの境界面の岩塊は普通数十kmにわたって硬く結び付いており、このような広範囲の固着域をアスペリティという。大きなアスペリティがずれると、周辺の固着していない部分も同時にずれ、さらに、その周辺の固着域にも力が及んで同時にずれ、このようにして境界上の広い面積が同時にずれるので、巨大地震となる。地震動から推定される規模のわりに津波が大きい地震を津波地震といい、1896年の明治三陸地震が典型的な津波地震の例とされている。
(2) 津波について
津波は、地震の断層運動等によって海底が広範囲にわたって急激に変動することで、海底の上に存在する海水が横方向へ逃げることなく鉛直変形分の海面隆起となり、波の進行方向へ海水全体が流動することで発生し伝播する現象である。津波には、伝播速度が水深の平方根に比例し、海底の等深線の垂直方向に進行するという性質がある。福島県沖の海底地形は、太平洋岸の海岸線が概ね北-南方向であるのに対し、海底の等深線が概ね北北東-南南西方向であり、南側の方が水深が深くなっている。そのため、福島県沖の日本海溝寄りで発生した津波は、南東の方角から本件発電所の敷地に襲来することになる。
2 本件発電所の原子炉の設置許可等
本件発電所においては、昭和41年12月に1号機の設置が許可され、その後昭和47年1月までに順次2号機から4号機までの増設のための設置変更が許可され、昭和46年3月から昭和53年10月までに1号機から4号機までが順次運転を開始した。また、5号機及び6号機も増設のための設置変更が許可されて、昭和53年4月から昭和54年10月までに運転を開始した。
以上の各号機の設置及び設置変更(増設)許可申請に際しては、既往最高潮位として昭和35年(1960年)のチリ地震津波によるO.P.+3.122mが設計津波水位として定められていた。この設計津波水位を含む基本設計は、上記各許可に際し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の要求する「原子炉施設の位置、構造及び設備が原子炉による災害の防止上支障がないものであること」という基準に適合することが認められ、4号機から6号機までの増設のための設置変更許可に際しては、当時の原子力委員会が昭和45年4月23日に策定した「軽水炉についての安全設計に関する審査指針」の要求する「過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること」という基準に適合することが認められた。また、上記の基本設計は、本件地震発生までの間、上記の各基準に加え、電気事業法及び同法に基づく省令の要求する、「原子炉施設が想定される自然現象(津波を含む。)により原子炉の安全性を損なうおそれ」がないという技術基準にも適合することが認められてきた。
以上のとおり、本件発電所は、法令やこれを補完する審査指針、技術基準などによって要求された安全性を確保しているものとして設置許可及び設置変更(増設)許可を得ており、その後、本件地震発生までの間、法令の要求する基準に適合することが認められていたものである。
3 土木学会の津波評価技術
(1) 津波評価技術の公表に至る経緯
ア 北海道南西沖地震の発生とこれを受けた津波の安全性評価
平成5年7月、北海道南西沖地震により日本海沿岸地域に津波被害が発生したことを踏まえ、資源エネルギー庁は、同年秋頃、東京電力を含む電気事業者に対し、既設の原子力発電所に対する津波の安全性評価を実施するよう指示した。これを受けて、東京電力は、本件発電所に対する津波の安全性評価を実施し、文献調査結果に基づき本件発電所の敷地及び敷地周辺に比較的大きな痕跡高を残したと考えられる既往津波を抽出し、予測式により敷地に襲来する津波の高さを推定し、その予測高が相対的に大きい1611年の慶長三陸地震津波、1677年の延宝房総沖地震津波及び1960年のチリ地震津波について、数値シミュレーションを実施した結果、本件発電所の護岸前面での最大水位上昇量は1960年チリ地震津波による値が最も大きく、最高水位がO.P.+3.5m程度になるが、護岸の天端高がO.P.+4.5mで、主要施設の整地地盤高がO.P.+10m以上であることから、津波が遡上したり、主要施設が津波による被害を受けることはないと評価し、平成6年3月、資源エネルギー庁に対し、その評価結果を報告した。
イ 4省庁報告書及び7省庁手引きの策定とこれを受けた津波の安全性評価
農林水産省構造改善局、同省水産庁、運輸省港湾局及び建設省河川局は、学識経験者及び関係機関からなる太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査委員会(津波工学を専門とする首藤伸夫東北大学教授(肩書は当時のもの、以下同じ。)、地震学及び津波学の大家である阿部勝征東京大学教授らが委員を務めていた。)を設置し、その指導と助言の下に調査を進め、平成9年3月付けで「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」(以下「4省庁報告書」という。)を取りまとめた。4省庁報告書は、総合的な津波防災対策計画を進めるための手法を検討することを目的として、太平洋沿岸部を対象として、過去に発生した地震・津波の規模及び被害状況を踏まえ、想定し得る最大規模の地震を検討し、それにより発生する津波について、概略的な精度であるが津波数値解析を行い津波高の傾向や海岸保全施設との関係について概略的な把握を行ったものである。4省庁報告書は、津波数値解析を行う想定地震の設定に当たって、①想定地震の設定規模は歴史地震も含め既往最大級の地震規模を用い、②想定地震の地域区分は地震地体構造論上の知見に基づき設定し、③想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅するように設定するという方針に従い検討を行っていた。その地域区分については、当時広く知られていた区分案として「日本列島の地震(地震工学と地震地体構造)」(萩原尊禮編、1991年)によって提案された地体区分を用いており、三陸沖を「G2」に、福島県沖から房総沖を「G3」に区分していた。
また、国土庁、農林水産省構造改善局、同省水産庁、運輸省、気象庁、建設省及び消防庁は、平成9年3月、「地域防災計画における津波対策強化の手引き」(以下「7省庁手引き」という。)を取りまとめた。7省庁手引きは、防災に携わる行政機関が、沿岸地域を対象として地域防災計画における津波対策の強化を図るため、津波防災対策の基本的な考え方、津波に係る防災計画の基本方針、防災計画の策定手順等について取りまとめたものである。この7省庁手引きには、「津波防災計画策定の前提条件となる外力として対象津波を設定する。対象津波については、過去に当該沿岸地域で発生し、痕跡高などの津波情報を比較的精度良く、しかも数多く得られている津波の中から、既往最大の津波を選定し、それを対象とすることを基本とする。ただし、近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については、別途現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を検討し、既往最大津波との比較検討を行った上で、常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するものとする。」と記載されていた。
4省庁報告書及び7省庁手引きが既往津波に加えて想定される地震に伴う津波を検討対象としていることから、東京電力を含む電力会社で構成される任意団体である電気事業連合会(以下「電事連」という。)の津波対応ワーキンググループは、平成9年7月25日、津波高さの検討を行い、4省庁報告書に示されている波源モデルを使って数値解析を行った結果、本件発電所の津波高さが最大でO.P.+4.8mとなり、想定地震の断層パラメータのばらつき及び計算誤差を考慮して、仮に2倍の津波高さの変動があるものとすると、水位上昇によって冷却水取水ポンプモーターが浸水することを確認した。また、東京電力は、想定される津波に対する本件発電所の安全性について検討を行い、平成10年6月、その報告書「津波に対する安全性について(太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査)」を公表した。同報告書には、4省庁報告書に示された断層モデルに基づき津波水位を計算した結果、本件発電所の最高水位がO.P.+4.8mとなり、屋外に設置されている非常用海水ポンプの据付レベルを超えるが、ポンプのモーター下端レベルには達しないため、安全性への影響はない旨記載されていた。
(2) 津波評価技術の公表とこれを受けた東京電力の対応
東京電力を含む電気事業者らは、想定津波及びその安全性評価法を統一的に取りまとめた技術指針的なものがなく、そのため、津波版民間技術指針の策定が望まれているとして、公益社団法人土木学会(以下「土木学会」という。)に対し、津波水位評価手法の体系化を委託した。土木学会原子力土木委員会の下に津波評価部会(首藤が主査を務め、阿部、地震学及び津波学の第一人者であり経済産業省工業技術院地質調査所に所属していた佐竹健治、津波工学を専門とする今村文彦東北大学教授ら地震や津波の専門家並びに電力会社の担当者等が委員を務めていた。)が設置され、同部会(第1期)は、津波波源に関する検討及び数値解析に関する検討について議論、審議を行い、平成14年2月、「原子力発電所の津波評価技術」(以下「津波評価技術」という。)を公表した。
津波評価技術は、それまで培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して、7省庁手引きを補完するものとして、原子力施設の設計津波水位の標準的な設定方法を提案したものである。その方法の概要は、「(1) 評価地点に最も影響を与える想定津波を設計想定津波として選定し、それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。(2) 想定津波の波源の不確定性を設計津波水位に反映させるため、基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施するパラメータスタディを行い、その結果得られる想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。(3) 設計想定津波の妥当性の確認は、①評価地点において設計想定津波の計算結果と既往津波の計算結果を比較すること、②評価地点付近において想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高を比較することによって行う。(4) 上記(1)~(3)に先立ち、既往津波の痕跡高の再現計算を実施することにより、数値計算に基づく評価方法の妥当性の確認を行う。」というものであった。そして、上記(1)から(4)までに基づき、想定津波の対象は近地津波(日本沿岸で発生する津波を指し、外国沿岸で発生するものを遠地津波という。)とすることを基本とし、プレート境界付近、日本海東縁部及び海域活断層に想定される地震に伴う津波を考慮することや、太平洋側のプレート境界付近に想定される地震の最大モーメントマグニチュードは、原則として各海域における既往最大の地震規模とすることなどの基本的事項に従って評価の検討をするとされた。その上で、プレート境界付近に想定される地震に伴う波源の設定に関しては、「太平洋沿岸のようなプレート境界型の地震が歴史上繰返し発生している沿岸地域については、各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考えられるが、念のため、プレート境界付近に将来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象とし、地震地体構造の知見を踏まえて波源を設定する。」、「波源設定のための領域区分は、地震地体構造の知見に基づくものとする。また、基準断層モデルの波源位置は、過去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ、合理的と考えられる位置に津波の発生様式に応じて設定することができる。」、「萩原編(1991)の地震地体構造区分図は、地形・地質学的あるいは地球物理学的な量の共通性をもとにした比較的大きな構造区分でとりまとめられているが、過去の地震津波の発生状況をみると、各構造区の中で一様に特定の地震規模、発生様式の地震津波が発生しているわけではない。そこで、実際の想定津波の評価にあたっては、基準断層モデルの波源位置は、過去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ、合理的と考えられるさらに詳細に区分された位置に津波の発生様式に応じて設定することができるものとする。」としていた。その上で、「日本海溝沿い海域では、北部と南部の活動に大きな違いがある点が特徴である。(中略)北部では、海溝付近に大津波の波源域が集中しており(中略)津波地震、正断層地震もみられる。一方、南部では、1677年房総沖地震を除き、海溝付近に大津波の波源域は見られず、陸域に比較的近い領域で発生している。(中略)福島県沖で記録されている大地震は1938年福島県東方沖(塩屋沖)群発地震のみである。」として、別紙3のとおり、三陸沖と房総沖の日本海溝沿いには波源設定のための領域を設定していたのに対し、両者の間にある福島県沖と茨城県沖の日本海溝沿いには波源設定のための領域を設定していなかった。なお、津波評価技術のまえがきには、「設計津波の設定技術については、(中略)最近の発生事象を契機として発展しつつある分野であるため、これらの事象から新たに得られてくる種々の知見等を柔軟に取り込んでいきながら、発電所の安全性、信頼性をより一層高めていくことが重要であると考えられる。」と記載されていた。また、津波評価技術(付属編)には、津波評価技術に基づいて計算される設計想定津波が、三陸海岸、熊野灘及び日本海東縁部の評価例として示された全185地点において、平均的には既往津波の痕跡高の約2倍となっていることが確認された旨、そのデータと共に記載されていた。
津波評価技術の公表を受けて、東京電力は、津波評価技術により想定される津波に対する本件発電所の安全性について検討を行い、平成14年3月、「津波の検討-土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討-」を公表した。その検討結果は、設計想定津波の最高水位が、福島沖プレート境界にMw8.0の波源を設定した場合におけるO.P.+5.7mというものであり、これが6号機の非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプの電動機据付レベルを上回るため、同ポンプ電動機のかさ上げ等の対策を実施するというものであった。
(3) 以上のとおり、東京電力は、本件発電所について、法令によって要求された安全性を確保するだけでなく、4省庁報告書及び7省庁手引きの策定を受けて津波の安全性評価を行い、さらに津波評価技術が公表されると、それに基づく想定津波水位に対応した自主的な対策工事を実施していた。
そして、津波評価技術が定める津波水位の評価手法は、後記のバックチェックルールが求める津波水位の評価手法と合致するほか、原子力等のエネルギーに係る安全及び産業保安の確保を図るために設置された保安院や、原子力利用に関する政策又は重要事項のうち、安全確保のための規制に関する政策又は規制に係るものに関する事項について企画し、審議し及び決定する原子力安全委員会における安全審査でも用いられていたものである。また、津波評価技術の公表当時、経済産業省設置法に基づいて設置された資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会(同法18条)の原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会が取りまとめた報告書「原子力発電施設の技術基準の性能規定化と民間規格の活用に向けて」によって、原子力発電所の安全性を確保するに当たっては民間規格を活用する方針が示され、この方針は安全規制に関わる者の間で広く共有されて、社団法人日本電気協会原子力規格委員会が平成19年に制定した「原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601-2008)」でも、津波水位評価は津波評価技術によると定められており、津波評価技術が定める津波水位の評価手法に従うことは、このような民間規格の活用の趣旨にも沿うものであった。
4 「長期評価」の公表
(1) 「長期評価」の公表とこれを受けた東京電力の対応
平成7年1月の兵庫県南部地震(いわゆる阪神・淡路大震災)の発生を受けて、同年、地震防災対策特別措置法に基づき総理府(後に文部科学省)に設置された地震本部は、平成14年7月31日、三陸沖から房総沖までの領域を対象とし、長期的な観点で地震発生の可能性、震源域の形態等について評価して取りまとめた「長期評価」すなわち「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」を公表した。
「長期評価」は、ごく大掴みにいえば、別紙4のとおり、三陸沖から房総沖までの領域を8つに分け、三陸沖北部から房総沖の海溝寄り(南北約800km、東西約70km)を一つの領域(以下「海溝寄り領域」という。)とした上で、同領域におけるプレート間大地震(津波地震)について、1896年の明治三陸地震と同様のMt8.2前後の地震が同領域内のどこでも発生する可能性があり、今後30年以内の発生確率は20%程度であることなどを内容とするものである。なお、Mtとは、津波マグニチュードのことであり、津波の高さの分布を使って算出する地震の大きさの指標である。
このような「長期評価」の公表を受けて、東京電力の土木グループは、平成14年8月、保安院の担当者から、①太平洋岸の原子力発電所の安全性、②津波評価技術が福島県沖と茨城県沖で津波地震を想定していない理由を問われ、①津波評価技術に基づいて安全性を確認していることから原子力発電所の安全性に問題はなく、②福島県沖から茨城県沖の海溝沿いでは有史以来津波地震が発生しておらず、三陸沖とは、プレート境界面の結合の強さや滑らかさ、沈み込んだ堆積物の状態が違う旨回答した。また、「長期評価」の見解については、土木学会で研究を予定していた確率論的津波ハザード解析の研究におけるロジックツリーの分岐の一つとして扱う方針であることを伝え、保安院の担当者から特段の異論は述べられなかった。
(2) 津波ハザード解析と同解析における「長期評価」の見解の扱い
ア 土木学会津波評価部会における津波評価技術の体系化に関する研究
土木学会津波評価部会(第2期)は、平成15年6月から平成17年9月までの間、確率論に立脚した津波評価手法の体系化等を目的として、津波水位の確率論的評価法に関する検討等について議論、審議を行い、平成17年9月、「津波評価技術の体系化に関する研究(その2)」を作成した。その内容は、津波水位の確率論的評価法のモデル化と評価手順の具体的提示などを行うものであった。
また、土木学会津波評価部会(第3期)は、平成19年1月から平成21年3月までの間、津波ハザード解析及び津波による海底地形変化評価手法の体系化を目的として、議論、審議を行い、平成21年3月、「津波評価技術の体系化に関する研究(その3)」を作成し、「確率論的津波ハザード解析の方法(案)」を公表した。その内容は、実務的に原子力発電所の確率論的津波ハザード解析を実施する場合の具体的方法の提示などを行うものであった。
イ 東京電力の東電設計に対する津波ハザード解析委託
上記のような土木学会津波評価部会における議論、審議と並行して、東京電力は、津波について確率論的な手法で評価を行うこと等を目的として、平成15年8月、東電設計に対し、本件発電所及び福島第二原子力発電所を対象地点とした津波ハザード解析を委託し、平成16年12月、東電設計から、「既設プラントに対する津波ハザード解析委託報告書」を受領した。津波ハザード解析とは、地震の位置、規模、発生頻度、発生様式等を確率分布として表現することにより、将来発生する津波による水位の超過頻度を求めるための解析であるが、本件発電所の1号機から4号機までの津波ハザード曲線(近地津波及び遠地津波)は、津波高さO.P.+10mの年超過確率が、フラクタイル(多数の専門家のうち同意する者の割合を表す。)算術平均で10のマイナス5乗よりもやや低い頻度であり6号機のそれは、フラクタイル算術平均で10のマイナス4乗と5乗の間の頻度であった。この解析結果は、「長期評価」の見解を踏まえ、日本海溝寄り津波地震について、①過去に発生例がある三陸沖(JTT1)及び房総沖(JTT3)は活動的だが、発生例のない福島県沖(JTT2)は活動的でないとする見解と、②これらは一体の活動域で、活動域内のどこでも津波地震が発生するとする見解をロジックツリーの分岐として設定し、土木学会津波評価部会が平成16年に実施した、上記の分岐に関する重み付けをするためのアンケートの結果を参考にして、①と②の見解に各O.5の重み付けをして得られたものであるところ、そのアンケートにおける地震学者ら6名(阿部、地震学を専門とする島村邦彦東京大学教授、佐竹、歴史地震及び津波学を専門とする都司嘉宣東京大学助教授、地震学の専門家である海野徳仁東北大学助教授、同じく地震学の専門家である谷岡勇市郎北海道大学助教授)からの回答における重み付けの平均は、①の見解がO.4、②の見解がO.6であり(このうちの2名は、①の見解に0、②の見解に1の重み付けをした。)、専門家(地震学、津波工学、地震工学又は海岸工学を専門とする者)9名の回答における重み付けの平均は、①の見解がO.46、②の見解がO.54であった。
また、東京電力は、平成21年11月頃、東電設計に対し、土木学会津波評価部会(第3期)が同年3月に公表した前記の「確率論的津波ハザード解析の方法(案)」に基づき津波ハザード解析を委託し、本件地震後の平成23年3月28日、東電設計から「既設プラントに対する津波ハザード解析委託(その2)報告書」を受領した。同報告書には、本件発電所4号機のハザード曲線が記載されており、そのハザード曲線(全体領域、長期間平均)は、津波高さO.P.+10mの年超過確率が、フラクタイル算術平均で10のマイナス4乗よりもやや低い頻度であった。この解析結果は、同じく「長期評価」の見解を踏まえ、日本海溝寄り津波地震について、①過去に発生例がある三陸沖と房総沖でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生するとする見解、②活動域内のどこでも津波地震が発生するが、北部領域に比べ南部ではすべり量が小さい(北部領域内では1896年の明治三陸地震モデル、南部領域内では1677年の延宝房総沖地震モデルを移動させる)とする見解、③活動域内のどこでも津波地震(1896年タイプ)が発生し、南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する(領域全体の中で1896年モデルを移動させる)とする見解をロジックツリーの分岐として設定し、土木学会津波評価部会が平成21年に実施した、上記の分岐に関する重み付けをするためのアンケートの結果を参考にして、各見解に①O.4、②O.35、③O.25の重み付けをして得られたものであるところ、そのアンケートにおける専門家(地震学又は津波工学を専門とする者)11名からの回答における重み付けの平均は、①の見解がO.35、②の見解がO.32、③の見解がO.33であった。なお、同報告書記載の解析結果は、その提出に先立つ平成22年末頃以降に、速報値が東京電力の土木グループに伝えられた可能性があるが、本件地震前にその内容が土木グループ外の者と共有されることはなかった。
ウ 発電用軽水型原子炉施設の性能目標の定量的な指標値案
原子力安全委員会安全目標専門部会は、平成18年3月28日、「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について-安全目標案に対応する性能目標について-」と題する報告書を取りまとめ、同年4月6日、原子力安全委員会に報告した。その内容は、発電炉の安全確保の水準を表し、安全目標への適合性を判断するための性能目標の定量的な指標値案として、炉心に内蔵される放射性物質の放出をもたらす炉心損傷の発生確率である炉心損傷頻度を10のマイナス4乗/年程度、格納容器の防護機能喪失の発生確率である格納容器機能喪失頻度を10のマイナス5乗/年程度と定め、両方が同時に満足されることを発電炉に関する性能目標の適用の条件とするというものであった。なお、電事連耐震指針検討チームが平成18年12月に取りまとめた資料によれば、工学的に無視できるレベルとして「例えば10のマイナス7乗回/年」とされている。
エ 津波ハザード解析に関するマイアミ論文の発表
東京電力の土木グループのグループマネージャーであった酒井俊朗、東電設計社員であった安中正らは、平成18年7月、米国フロリダ州マイアミで開催された原子力工学に関する国際会議において、「日本における確率論的津波ハザード解析法の開発」と題する論文(以下「マイアミ論文」という。)を発表した。同論文は、確率論的津波ハザードの検討手法を紹介するものであり、「JTT系列(日本海溝沿いの領域)はいずれも似通った沈み込み状態に沿って位置しているため、日本海溝沿いのすべてのJTT系列において津波地震が発生すると仮定できる可能性がある。他方では、JTT2(福島県沖)では既往津波が確認されていないことから、津波地震はJTT1(三陸沖)とJTT3(房総沖)のみで発生すると仮定できる可能性がある。」と記載されていた。
(3) 地震本部地震調査委員会は、平成15年3月24日、「千島海溝沿いの地震活動の長期評価について」を公表した際、それまでに公表した評価の信頼度をA(高い)、B(中程度)、c(やや低い)、D(低い)の4段階にランク付けすることとした上で、「長期評価」における三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)について、海溝寄り領域を一つの領域としていた発生領域の評価の信頼度をCと評価するなどし、平成21年3月9日、「長期評価」を一部改訂した際に、この信頼度の評価を追加した。
(4) 以上のように、「長期評価」は、津波評価技術とは異なり、海溝寄り領域を一つの領域として、その領域内はどこでも、すなわち福島県沖でも、明治三陸地震と同様のMt8.2前後の地震が発生する可能性があるとするものであった。土木グループは、その公表当初、津波評価技術に基づく評価により本件発電所の安全性に問題はなく、「長期評価」を確率論的津波ハザード解析の研究におけるロジックツリーの分岐の一つとして扱う方針であったが、その後、平成16年12月には、本件発電所の1号機から4号機までの津波ハザード曲線について、津波高さO.P.+10mの年超過確率が、原子力安全委員会安全目標専門部会の示した「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について-安全目標案に対応する性能目標について-」の格納容器機能喪失頻度を下回るが、工学的に無視できるレベルとまではいえない10のマイナス5乗よりもやや低い頻度であることを把握しており、さらに平成22年末頃には、本件発電所4号機の津波ハザード曲線について、津波高さO.P.+1Omの年超過確率が、前記の格納容器機能喪失頻度を上回る10のマイナス4乗よりもやや低い頻度であることを把握していた可能性がある。その一方で、地震本部は、後に「長期評価」について信頼度の評価を行い、海溝寄り領域を一つの領域とする発生領域の評価の信頼度をCと評価するなどし、これを改訂版に追記した。
5 「発電用原子炉施設に関する耐震設許審査指針」の改訂
原子力安全委員会は、平成18年9月19日、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改訂した(以下、改訂後の指針を「新指針」といい、改訂前のものを「旧指針」という。)。旧指針は、昭和53年9月、当時の原子力委員会が、発電用原子炉施設の耐震設計に関する安全審査を行うに当たって、その設計方針の妥当性を評価するための審査上の指針として集約を行ったものであり、その「基本方針」として、「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない。」と記載されていた(なお、旧指針は、昭和56年7月及び平成13年3月に、原子力安全委員会によって一部改訂がされている。)。新指針は、発電用軽水型原子炉の設置許可申請(変更許可申請を含む。)に関する安全審査のうち、耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定められたものであり、それまでの地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積並びに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良及び進歩を反映し、旧指針を全面的に見直したものである。新指針は、基本方針として、「耐震設計上重要な施設は、敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない。」と定めていた。そして、その解説には、「地震学的見地からは、(中略)策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性は否定できない。このことは、耐震設計用の地震動の策定において、「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。したがって、施設の設計に当たっては、策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を払い、基本設計の段階のみならず、それ以降の段階も含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。」、「策定された地震動の応答スペクトルがどの程度の超過確率に相当するかを把握しておくことが望ましいとの観点から、それぞれが対応する超過確率を安全審査において参照することとする。」と記載されていた。また、新指針は、「地震随伴事象に対する考慮」として、「施設は、地震随伴事象について、次に示す事項を十分考慮したうえで設計されなければならない。(中略)施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」と定めていた。
6 新指針を受けた耐震バックチェックの指示
(1) 原子力安全委員会からの耐震バックチェックの指示
原子力安全委員会は、平成18年9月19日、「「耐震設計審査指針」の改訂を機に実施を要望する既設の発電用原子炉施設等に関する耐震安全性の確認について」を決定した。同決定には、「既設の原子力施設の耐震安全性については、個別の安全審査において、それぞれ申請時における最新の科学技術的知見に基づく厳正な判断に基づき、耐震安全性を確保するための基本設計ないし基本的設計方針の妥当性が確認され、さらに所定のいわゆる後段規制の適用のもと、運転段階における耐震安全性の確保が図られてきたところである。ところで、原子力施設の安全性については、運転管理に直接携わる原子炉設置者等の原子力事業者のみならず、安全規制を担当する行政庁及び当委員会においても、常に最新の科学技術的知見に照らし合わせて、更なる安全性の向上に努めていくことが重要である。そこで、当委員会は、(中略)既設の原子力施設について、これらの改訂等がなされた安全審査指針類の規定内容を踏まえた耐震安全性の確認(以下「耐震バックチェック」という。)を実施することが、我が国の原子力施設の耐震安全性の一層の向上に資するものであり、国民への説明責任の観点から意義深いものと認識するものである。」、「今般改訂等がなされた(中略)安全審査指針類については、今後の安全審査等に用いることを第一義的な目的としており、指針類の改訂等がなされたからといって、既設の原子力施設の耐震設計方針に関する安全審査のやり直しを必要とするものでもなければ、個別の原子炉施設の設置許可又は各種の事業許可等を無効とするものでもない。すなわち、上述の既設の原子力施設に関する耐震安全性の確認は、あくまでも法令に基づく規制行為の外側で、原子炉設置者等の原子力事業者が自主的に実施すべき活動として位置づけられるべきであるものの、当委員会としては、既設の原子力施設の耐震安全性の一層の向上に資する観点から、行政庁による対応について、その着実な実施を特に求めるものである。また、既設の原子力施設の「残余のリスク」に関する定量的評価については、確率論的安全評価(PSA)に代表される最新の知見に基づいた評価手法を積極的に取り入れていくことが望ましいと考える。」と記載されていた。
(2) 保安院によるバックチェックルールの策定
新指針の策定を受け、保安院は、平成18年9月20日、東京電力を含む原子力事業者に対し、既設発電用原子炉施設について、新指針に照らした耐震安全性の評価を実施するとともに、将来の確率論的安全評価の安全規制への導入の検討に資する情報として、「残余のリスク」の評価を実施し、それぞれその結果を保安院に報告するよう求め、原子力事業者から報告を受けた評価結果については、保安院がその妥当性を確認した上、その結果を原子力安全委員会に報告することとされた。保安院は、同日、「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」を作成し、耐震バックチェックに当たっての基本的な考え方を示した上で、①事業者が新指針に照らして耐震安全性を評価するための基準的な手法、②事業者が行った評価結果を保安院において確認するための基準を示した(以下「バックチェックルール」という。)。バックチェックルールには、評価手法及び確認基準の項目として、「地震随伴事象に対する考慮」の項に「津波に対する安全性」が列挙されているところ、これに関しては、評価手法として、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波を想定する。」と記載され、その解説には、「津波の評価に当たっては、既往の津波の発生状況、活断層の分布状況、最新の知見等を考慮して、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し、数値シミュレーションにより評価することを基本とする。」、「想定津波の数値シミュレーションに当たっては、既往の津波の数値シミュレーションを踏まえ、想定津波の断層モデルに係る不確定性を合理的な範囲で考慮したパラメータスタディーを行い、これらの想定津波群による水位の中から敷地に最も影響を与える上昇水位及び下降水位を求め、これに潮位を考慮したものを評価用の津波水位とする。」と記載されていた。
(3) 東京電力の対応
耐震バックチェックの指示を受けて、東京電力は、本件発電所につき、津波評価技術公表時に再評価、所要の対策を実施済みであり、過去最大の津波及び想定される最大規模の津波に対しても安全性が確保されているという方針で対応することとした。
保安院は、平成18年10月6日、東京電力を含む原子力事業者に対する一括ヒアリングを行い、原子力事業者の担当者に対し、津波(高波)について、耐震バックチェックで津波に対する対応策を確認すること、津波高さと敷地高さがあまり変わらないサイトがあるが、自然現象であって、設計想定を超える津波が来るおそれがあり、その場合、非常用海水ポンプが機能喪失し、そのまま炉心損傷に至る可能性があることを指摘して、早急に対応を検討するよう指示した。
東京電力は、平成19年1月に電事連において取りまとめられた津波対策に関する基本方針、すなわち、バックチェック報告時には、土木学会手法(すなわち津波評価技術)の妥当性を説明するとともに、当該津波高さに対する評価結果を報告すること、十分保守的な土木学会手法による津波に対し、余裕を更に向上させ、将来的な津波ハザード評価結果を見据えた事前準備として、津波対策を自主的対策として実施すること、自主的対策の要否の判断については、暫定的な津波ハザードないし津波の確率論的安全評価の結果を参考とすること、考え方及び対策は可能な限り電力各社で足並みを揃えること、裕度が小さい設備に対しては、電力各社の個々の事情を踏まえて個別に対応の要否を検討してよいことという基本方針に従い、同年4月4日、保安院に対し、自主的な対策として、想定津波(押波)に対する余裕がない本件発電所の非常用海水ポンプについては、電動機の水密化や建屋の追設といった対策を実施する方向で検討を行うことを伝えた。
(4) 以上のとおり、発電用軽水型原子炉の耐震安全性確保のための新指針の策定を受けて原子力安全委員会から耐震バックチェックの指示がされ、併せて保安院から「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波を想定する。」などとするバックチェックルールが示されたところ、東京電力は、その当初、電事連で取りまとめられた津波対策に関する基本方針を踏まえて、本件発電所の津波安全性については、津波評価技術による評価、対策を実施済みであるが、必要な対策については、自主的な対策としてこれを実施する方向で検討するという方針を示していた。
7 新潟県中越沖地震を契機とした「中越沖地震対応打合せ」の開催
(1) 新潟県中越沖地震の発生
平成19年7月16日、新潟県中越沖地震が発生し、東京電力が設置、運転する新潟県柏崎市所在の柏崎刈羽原子力発電所において、観測された地震動が設計基準を大きく超えたほか、地震動による水面の揺動によって同発電所原子炉建屋の使用済み燃料プールから放射性物質を含む水が溢れ、その水が非放射性の排水収集タンクに流入するなどの事故が発生し、その後、同発電所の全号機が長期にわたり停止することとなった。これを受けて、経済産業大臣は、同月20日、東京電力に対し、新潟県中越沖地震から得られる知見を耐震安全性の評価に適切に反映することなどを指示した。
(2) 中越沖地震対応打合せの開催
東京電力では、柏崎刈羽原子力発電所の復旧を確実に進めるべく、関係部署間において情報を共有し、業務遂行の方向性につき共通の認識を持つ場として、社長(当時、被告人勝俣)、原子力・立地本部本部長(当時、被告人武黒)、同本部副本部長(当時、被告人武藤)、原子力設備管理部部長(当時、吉田昌郎)ら同本部の部長、柏崎刈羽原子力発電所の所長等の出席する「中越沖地震対応打合せ」(「御前会議」とも称されていた。)が、平成19年7月以降、月に1回程度の頻度で継続的に開催されるようになった。また、同年11月、原子力・立地本部原子力設備管理部内に新潟県中越沖地震への対応を専門的に進める組織として新潟県中越沖地震対策センター(以下「対策センター」という。)が設置され、同センターが新潟県中越沖地震で観測された地震動の解析評価、機器等の健全性確認評価、地震動の検討に必要な地質地盤調査等の業務に加え、本件発電所の耐震バックチェックに関する業務をも行うこととなり、中越沖地震対応打合せには、対策センター長(当時、山下和彦)、対策センター内の担当グループマネージャー、本件発電所及び福島第二原子力発電所の各所長も出席するようになった。この中越沖地震対応打合せにおいては、柏崎刈羽原子力発電所の復旧に関する事項が議題の中心であったが、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震安全性評価が議題となることもあり、耐震バックチェックの工程や耐震バックチェック報告書の内容が議題とされることもあった。なお、被告人勝俣は、代表取締役社長を退任し、代表取締役会長に就任した平成20年6月以降も、被告人武黒は、原子力・立地本部本部長を退任し、フェローに就任した平成22年6月以降も、それぞれ同打合せに出席していた。
8 平成20年2月16日開催の中越沖地震対応打合せ
平成20年2月16日、被告人ら3名、吉田、山下らが出席して中越沖地震対応打合せが開催された。この打合せにおける議題は4つあり、合計28丁の資料が配布された。議題の1つが対策センターを主管とする「Ssに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて」であり、同対策センター作成のA3用紙5丁からなる議題と同名の資料が配布された。同資料には、「1F/2F耐震設計審査指針改訂対応のポイント」として、「1.バックチェック基本計画 2.基準地震動の策定 3.耐震性向上工事の説明性確保 4.地震随伴事象である「津波」への確実な対応」の4つの項目が掲げられ、項目3の該当箇所には、「耐震性向上工事の打出し方 耐震バックチェック最終報告書提出までの工事完了は不可能 最終報告書提出時のプラント停止リスク回避」、項目4の該当箇所には、「津波高さの想定変更」、「津波高さ 従来+5.5m 見直し(案)+7.7m以上 詳細評価によってはさらに大きくなる可能性」、「理由 指針改訂に伴う基準地震動Ss策定において海溝沿いモデルを確定論的に取扱うこととしたため」と記載されていた。
ところで、山下は、この打合せにおいて、想定する津波高さの変更について自ら報告し、了承されたので、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むという東京電力としての方針が決められた旨供述している。これに対し、被告人ら3名は、公判において、山下から想定津波高さの変更の報告はなかったとした上で、何らかの方針が決定、了承されたり、方向性が確認されたこともないと供述している。上記の山下供述に関しては、機器耐震技術グループの山崎英一が後日作成した電子メールやメモに津波対応を社長会議で説明済みとの記載があるなど、山下供述の裏付けとなり得る証拠も存在する。しかしながら、この打合せの議事録には、当該議題に関する主要議事として基準地震動Ssに関する記載があるのに対し、津波に関する記載は一切ないことや、参加者として山崎の氏名が記載されておらず、同人が実際に同打合せに参加していたのかも定かではないことからすれば、山崎の前記のメールやメモの記載は、山崎が資料の配布をもって報告と表現したものである可能性を否定できない。また、同打合せの時点では、後記のとおり、東電設計に委託していた津波水位計算の正式な計算結果が伝えられておらず、方針の決定、了承又は方向性確認の前提となる情報が必ずしも揃ってはいなかったこと、土木グループの金戸俊道が後の平成20年5月に他の原子力事業者の担当者に対し海溝沿い地震の扱いについて東京電力の対応方針が未定である旨を伝えていることなど、この打合せにおいて東京電力としての方針が決定又は了承されるなどしたこととは整合しない事実も認められる。のみならず、仮にこの打合せで東京電力としての方針が決まっていたとすれば、後の同年6月に吉田や酒井ら土木グループの担当者が被告人武藤に耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り入れるか否かの方向性について相談することや、まして被告人武藤が同勝俣ら最上位の幹部がいる場で決まった方針をその一存でひっくり返すに等しい別の方針を示すことは考え難いところである。一方で、山下としては、自らが被疑者として取調べを受ける中で当該記載のある資料を配布した事実から推測で供述している可能性や、当該記載に対して席上誰からも指摘がなかったことをもって黙示の承認と受け取り、上記供述に至った可能性も拭えない。以上によれば、上記の山下供述の信用性には疑義があるといわざるを得ず、被告人らには、同打合せの配布資料に記載された、O.P.+5.5mからO.P.+7.7m以上への津波高さの変更に関する情報を認識する契機があったとはいえるものの、それ以上に、津波高さの変更についての報告が行われて、これが了承され、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むという東京電力としての方針が決定されたといった事実までは、認定することができない。
9 「長期評価」に基づく東電設計によるパラメータスタディの実施
(1) 東京電力の土木グループ(当時、グループマネージャーの酒井、髙尾誠、金戸らが在籍していた。)は、平成19年12月上旬頃までには、「長期評価」の見解について、津波の検討では当初確率輪の中で取り扱うこととしていたが、基準地震動の策定に関する検討では確定論として取り扱うこととしたため、津波の検討でも確定論として取り扱わざるを得ず、「長期評価」の見解を明確に否定できなければこれを耐震バックチェックの津波評価に取り入れざるを得ないとの方向で対応することとし、その頃、関東以北の太平洋岸に原子力発電所を設置、保有する東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)や日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)等の他の原子力事業者の担当者らにその方向性を伝えるとともに、耐震バックチェックへの対応を検討するに当たり、「長期評価」の見解を取り込んだ場合の影響を把握するために、東電設計に津波水位計算を委託することとした。東京電力は、平成20年1月11日、東電設計に対し、本件発電所及び福島第二原子力発電所前面の日本海溝寄りプレート間地震による想定津波についてパラメータスタディを行い、本件発電所等における津波水位を計算するよう委託した。委託に先立つ担当者間の打合せにおいて、「長期評価」による三陸沖北部から房総沖の海溝寄りプレート間大地震(津波地震)の想定津波が検討対象の一つとされていた。東電設計は、正式な委託に先立ち、前記の津波ハザード解析で検討していた計算結果を一部利用して、本件発電所前面の日本海溝寄りのプレート境界地震のモデル(Mw8.3)につき、概略的な津波高さを計算したところ、朔望平均満潮位における最高水位が6号機前面でO.P.+7.7m、詳細パラメータスタディを実施した場合は更に水位が高くなる見込みであるという計算結果を得て、平成19年11月21日、髙尾らに対し、その計算結果を伝えた。酒井は、平成20年1月末頃までに、吉田及び山下に、「長期評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り入れざるを得ないという上記の方向性と、O.P.+7.7mとの概略計算結果を伝えた。酒井は、その頃、他の担当者らに対して、「津波は「NG」の話は2月1日サイトに説明します。」(同年1月23日)、「I津波がNGとなると、プラントを停止させないロジックが必要。」(同年2月4日)といったメールを送信するなど、「長期評価」の見解を津波評価に取り込んだ場合、本件発電所における想定津波水位が当時の設計水位O.P.+5.7mを超えることが確実であり、これに対する対策工事が未了の場合、対外的な説明性の観点、すなわち、原子炉を運転しながら工事を行うことを対外的に公表して説明し理解を得るのは容易ではないという観点から、原子炉の運転停止に追い込まれる可能性があるとの認識を有していた。
(2) 平成20年2月1日、山下、酒井らは、本件発電所所長らに対し、耐震バックチェックの進捗状況等を説明した。その説明資料には、「推本が示す海溝沿いの震源モデルについては、津波の検討では、当初確定論で扱わず、確率論の中で取り扱うこととしていた。一方、Ss(施設の耐震設計において基準とする地震動であり、敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めて稀ではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定することが適切なものとして策定されるものをいう。)策定に関する検討では、推本の見解を無視できないとの判断から確定論として取り扱うこととしたため、津波の検討においても海溝沿いの震源モデルを考慮する必要が生じている。既往の想定津波評価では、Ss策定のために設定している震源モデルの位置に波源モデルを設定しておらず、この震源モデルの位置に津波の波源モデルを設定すれば、これまでの想定津波高さを上昇側は上回り、下降側は下回る可能性が高い。(上記モデルについて過去に概略検討した結果から、1F-6取水口前面で約T.P.(「O.P.」の誤記と考えられる。)+7.7mとの結果が得られているが、詳細検討を実施すればさらに大きくなる可能性がある。 (参考)既往の評価結果 福島第一 上昇側評価結果 津波水位O.P.+5.7m」と記載されていた。このような説明に対して、本件発電所の職員から、津波高さが7mではハード的な対応が不可能ではないかという懸念が示された。
(3) 土木グループでは、「長期評価」の見解を考慮する必要性が高いものの、最近の研究の動向や有識者の見解等を踏まえて津波に対する安全性評価への反映の要否、改造工事の検討等について判断する必要があると考え、髙尾が、平成20年2月26日、保安院における耐震バックチェック審査を行う作業部会(本件発電所を担当)の委員を務める今村に対し、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むべきかどうかについて相談した。今村は、①「長期評価」の議論に参加していないので「長期評価」に対してはコメントできない、②福島県沖海溝沿いで大地震が発生するかどうかについて、繰り返し性がなく、切迫性もないことを理由に中央防災会議では結論を出さなかったが、大地震が発生することは否定できないので、波源として考慮し、数値解析を行って検討を進めていくべきである、③その波源モデルは、既往津波のものを使うのであれば、津波地震については明治三陸地震と延宝房総沖地震のものを使うしかない、④既往津波の記録が得られていないので、今後津波堆積物の研究が重要となる旨の意見を述べた。土木グループでは、今村の意見を踏まえ、引き続き「長期評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り入れざるを得ないとの方向性で対応に当たることとした。髙尾は、同月27日、東京電力の津波対策の担当者らに対し、土木グループで、津波数値計算を実施中であるが、大幅改造工事を伴うことは確実である旨のコメントを付して、今村の意見を報告した。また、同年3月5日、関東以北の太平洋岸に原子力発電所を設置、保有する他の原子力事業者らとの耐震バックチェックに関する打合せ等において、今村の意見を報告するとともに、「長期評価」の見解を否定することは決定的な根拠がない限り不可能と判断したこと、津波地震として明治三陸地震と延宝房総沖地震の波源モデルを用いて津波評価技術の手法によるパラメータスタディを実施する予定であること、原子炉施設等が浸水するような解析結果となった場合、施設の水密化や手順書の作成等を予定していることを報告した。
(4) 本件発電所の耐震バックチェックへの対応を担当する関係グループの担当者らは、津波水位の評価が従前よりも大幅に上がる可能性があったことから、その対応策を検討するため、平成20年3月7日、津波対策の工程に関する打合せを行った。その際、金戸が、津波の高さがO.P.+12ないし13m程度になる可能性が高い旨説明したのに対し、機器耐震技術グループの担当者から、O.P.+1Omを超えると主要建屋に水が流入するため、対策が大きく変わるとの指摘があり、土木グループにおいて、水位設定条件を再度確認した上、想定津波高さが十数mとなる可能性のあることを上層部へ周知することとされた。
(5) 平成20年3月11日、被告人武黒らが出席して常務会が開催され、吉田らから、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェック中間報告を行うことの提案があり、審議の結果、了承、決定された。その際、同中間報告の内容を、①地質調査(途中経過)、②基準地震動Ss、③本件発電所5号機等の原子炉建屋及び重要設備の評価結果とすることが説明された。配布された資料には、耐震バックチェックの全体スケジュールとして、本件発電所では5号機を対象として平成20年3月末に中間報告を、平成21年6月に最終報告を行うことなどが記載されていた。また、同資料には、リスクとして、「津波の評価 プレート間地震等の想定が大きくなることに伴い、従前の評価を上回る可能性有り」と記載されていた。
(6) 東電設計は、東京電力の委託を受けて、明治三陸地震の波源モデル(Mw8.3)を宮城県金華山沖から房総沖までのプレート間の領域に設定してパラメータスタディを実施し、朔望平均満潮位で計算したところ、本件発電所における最大津波高さが敷地南側でO.P.+15.707mという計算結果を得た。髙尾、金戸らは、平成20年3月18日、東電設計の久保賀也らから、その計算結果を伝えられ、これを酒井らに報告し、酒井は、これを吉田に報告した。酒井、髙尾及び金戸は、いずれも津波対策の検討を実施する必要があると考え、その頃、金戸が、久保に対し、本件発電所の1号機から4号機までの主要建屋が設置されている10m盤並びに5号機及び6号機の主要建屋が設置されている13m盤を囲う鉛直壁(厚みはなく、高さは無限の仮想の壁であり、もとより工事の成立性を考慮に入れたものではない。)を設置した場合の最大津波高さ分布の解析を委託した。
(7) 平成20年3月20日、被告人武黒、同武藤、吉田、山下、酒井らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、耐震バックチェック中間報告の内容が確認されるとともに、同中間報告の地域説明に向けた想定問答案が配布された。その想定問答案には、津波の評価は、中間報告では行わず、地震随伴事象について現在解析・評価を行っているところであり、最終報告において結果を示す予定である旨記載されていた。同打合せでは、本件発電所の所長から、地震本部のモデル(すなわち「長期評価」)は福島県の防災モデルに取り込まれており、8m程度の数字は既に公開されていることから、最終報告で示すというのでは至近の対応ができない旨の意見が述べられた。これを受けて、土木グループは、同打合せ後、福島県が設定した想定断層モデルは、後記のとおり、中央防災会議のモデルであって、地震本部のモデルというのは本件発電所所長の誤解であること、津波高さが8m程度というのは防波堤等の海岸構造物を考慮しないものであり、海岸構造物を考慮した場合に安全上問題がなく、その旨国等に説明済みであることを確認した上、これらを想定問答案に追加した。確定した想定問答には、耐震バックチェックにおいて、「長期評価」の見解を「不確かさの考慮」という位置づけで考慮する計画である旨記載されるとともに、津波に対する評価の結果、施設への影響が無視できない場合、非常用海水ポンプ電動機が冠水し、故障することを想定した電動機予備品の準備、水密化した電動機の開発、建屋の水密化等が考えられる旨記載されることとなった。
(8) 東京電力は、平成20年3月31日、保安院に対し、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェック中間報告書を提出した。中間報告書は、本件発電所については、5号機における、敷地周辺・敷地近傍・敷地の地質及び地質構造、基準地震動Ssの策定、安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価、安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価を内容とするものであり、津波に対する安全性については、解析・評価を行っているところであり、最終報告において結果を示す予定である旨記載されていた。同報告書には、基準地震動の策定に当たり、地震本部は、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域において、M8クラスのプレート間地震を想定している。しかしながら、これらの地震は津波地震とされており、この領域で過去に発生した最大規模の地震である1896年明治三陸地震(M8.2)においても、震害はなかったとされていることから、敷地に及ぼす影響は小さいと考えられる。」として、「長期評価」が上記の領域に想定する地震を検討用地震に選定しなかったことが記載されていた。中間報告書の提出に合わせて、被告人武藤は、福島県生活環境部長に対し、耐震バックチェック中間報告の内容や今後の耐震安全性強化の取組みを説明したが、その際、県の担当者からの質問に対し、津波の評価については、最新の知見を踏まえて安全性の評価を行い、最終報告において報告する旨回答した。
(9) 東電設計は、東京電力の委託を受けて、本件発電所の1号機から4号機までの主要建屋が設置されている10m盤並びに5号機及び6号機の主要建屋が設置されている13m盤を囲う鉛直壁を設置した場合の最大津波高さ分布の解析を実施したところ、鉛直壁に当たる最大津波高さが敷地南護岸前面でO.P.+19.933mという計算結果を得て、金戸らは、平成20年4月18日、久保から、その計算結果を伝えられた。土木グループは、同月23日、地震動評価、建築設備技術を担当する建築グループ、土木設備技術を担当する土木技術グループ、建物内の設備技術を担当する機器耐震技術グループの各担当者らと、必要となる設備対策について打合せを行った。同打合せでは、想定津波高さが十数mとなる見込みであり、鉛直壁を設置した場合の最大津波高さが19m程度となる旨の上記の計算結果が示された上、壁を設置する場合、19m程度の津波を想定していることは対外的にインパクトが大きいと考えられるため、常務会等の上層部の意見を聴いておくこと、4m盤に設置された非常用海水ポンプの津波対策を検討していくことが確認された。
(10) 以上のとおり、土木グループは、本件発電所の耐震バックチェックの審査を行う作業部会の委員を務める専門家の意見も踏まえて、「長期評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り入れざるを得ないとして、取り入れた場合の影響を把握するために東電設計に本件発電所の津波水位計算を委託し、明治三陸地震の波源モデルを海溝寄り領域に設定したパラメータスタディにより、平成20年3月には最高津波水位が敷地南側でO.P.+約15.7m、翌4月には敷地を囲う鉛直壁を設置した場合の最大津波高さがO.P.+約19.9mという計算結果を伝えられ、大規模工事を行う場合、対外的な説明性の観点から原子炉の運転停止に追い込まれる可能性があることを認識しつつ、関係グループとの間で必要となる設備対策についての打合せを重ねるなどしていた。その一方で、耐震バックチェックに関しては、津波に対する安全性については解析・評価を行っているところであり、最終報告において結果を示す予定であるとして、平成20年3月に中間報告書を提出した。
10 被告人武藤に対する平成20年6月10日と同年7月31日の吉田部長らによる説明
(1) 被告人武藤に対する説明に至る経緯
土木グループの酒井、髙尾及び金戸は、平成20年6月2日頃、それまでの議論の経過を吉田に報告し、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むかどうか、取り込んだ場合の津波対策の進め方について相談した。吉田は、自身では判断がつかないとして、被告人武藤の判断を仰ぐこととなった。これと並行して、髙尾及び金戸は、同年5月16日及び同年6月5日、東電設計の久保らに対し、より精密な数値解析を行うこと又は津波対策工事を考慮することにより、津波高さを低減できないかの検討を依頼していたところ、同月9日までの間に、久保らから、より精密な数値解析を行っても津波高さの低減が見込めないこと、津波対策工事の考慮については、南側防波堤の付根部分に更に防潮堤を設置した場合に約4m程度の津波高さの低減効果が見込まれること、沖合に防波堤を設置した場合も津波高さの低減効果が見込まれることを伝えられ、関係資料の送付を受けた。
(2) 被告人武藤に対する平成20年6月10日の説明
吉田、山下、土木グループの酒井、髙尾及び金戸のほか、機器耐震技術グループ、建築グループ、土木技術グループの各担当者らは、平成20年6月10日、立地地域部で技術・広報を担当していた上津原勉も同席の上、被告人武藤に対し、本件発電所における津波評価の経緯を報告し、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むかどうか、取り込んだ場合の津波対策の進め方について指示を仰いだ。その報告に際しては、①本件発電所における津波の最高水位が津波評価技術によりO.P.+5.7mと評価され、この水位に対しては対策済みであること、②その後、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性がある旨の「長期評価」が公表されたが、福島県沖の海溝沿いを波源とする津波が起きたとする事実が得られていないことから、これを津波の確率論的安全評価におけるロジックツリーの分岐の一つとして扱うこととし、その分岐の重み付けに関するアンケートを実施した結果、地震学者の平均で上記地震が上記領域内のどこでも発生するが0.6、福島沖では発生しないが0.4であり、その結果に基づく本件発電所6号機(主要建屋が13m盤に設置されている。)の津波ハザード曲線は、津波高さO.P.+10mの年超過確率がフラクタイル算術平均で10のマイナス4乗と5乗の間の頻度、津波高さO.P.+13mの年超過確率が10のマイナス5乗と6乗の間の頻度であること、③耐震設計審査指針が改訂され、基準地震動Ss策定に際し、新指針が求める「不確かさの考慮」として福島県沖に海溝沿いの地震を想定したことに伴い、津波についても福島県沖の海溝沿いを波源とする津波を確定論として考慮するかどうかが問題となっていること、④その津波を考慮し、明治三陸地震のモデルを福島県沖の海溝沿いに設定してパラメータスタディを実施した場合、本件発電所敷地南側の津波最高水位がO.P.+15.7mとなること、⑤遡上域に鉛直壁の設置を仮定した場合に鉛直壁に当たる津波高さが敷地南側でO.P.+約20mとなること、⑥沖合に防波堤を設置すれば敷地への遡上水位を大幅に低減できるが、施工の成立性や必要な許認可の検討は未了であること、⑦当時平成21年6月と予定されていた耐震バックチェック最終報告時に津波対策工事が完了していないことを対外的にどのように説明するかについて、社内の意思決定が必要であることなどが説明された。加えて、酒井は、津波評価技術が過去の記録等に基づいて津波の波源領域を設定しているのに対し、「長期評価」の波源領域の設定には明確な根拠が示されておらず信頼性がないこと、しかし、耐震バックチェックの審査に関与している専門家が「長期評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り込むべきと言っているので、取り込まざるを得ないと考えていること、延宝房総沖地震のモデルを用いた場合、津波水位を低減できる可能性があることも説明した。これに対し、被告人武藤は、酒井らに対し、①津波ハザードの検討内容について詳細に説明すること、②4m盤への遡上高さを低減するための概略検討を行うこと、③沖合に防波堤を設置するために必要となる許認可を調べること、④並行して機器の対策についても検討することを指示し、これらの検討結果をまとめて再度打合せを行うこととした。
(3) 平成20年6月10日の説明後の検討状況
ア 金戸は、平成20年6月10日以降、久保に対し、①敷地南側から主要施設敷地への津波の遡上を抑制することを目的として、敷地南側に防潮堤を設置した場合及び沖合に防波堤を設置した場合の各津波高さの検討、②港湾内(既設防波堤の内側)の津波高さを低減させることを目的として、既設防波堤をかさ上げした場合の津波高さの検討を依頼し、同年7月22日までに、①敷地南側沖合に津波の進入方向に対し直交方向に防波堤を設けた場合の低減効果が最も大きく、前記鉛直壁前面の津波高さが、最大O.P.+12m程度に低減される旨、②既設防波堤を鉛直壁としても(いくらかさ上げしても)4m盤の浸水は防げない旨の検討結果を伝えられた。
イ 髙尾は、平成20年7月23日、他の原子力事業者らとの打合せにおいて、東京電力では対策工事を実施する意思決定までには至っていないこと、防潮堤や防潮壁といった対策工事の基本的な成立性の検討を10月までには終えたいこと、「長期評価」の見解に基づく津波も考慮すべきとの社内調整を進めていることを報告した。この打合せにおいて、日本原電の安保秀範は、陸域の押し波に対しては、地盤改良の際の排泥を利用した防潮堤、防水扉などの対策を、海水ポンプ室の押し波に対しては、蓋、壁などの対策をそれぞれ検討していること、日本海溝寄りの波源モデルとして延宝房総沖地震を設定することができないか検討していることを述べ、この打合せに出席していた東電設計の安中が、日本海溝の北部と南部を区分できる資料を追って作成することとなった。
(4) 被告人武藤に対する平成20年7月31日の説明
被告人武藤、吉田、山下並びに酒井、髙尾及び金戸ら、津波対策を担当するグループの担当者らは、平成20年7月31日、同年6月10日の議論を踏まえた打合せを行った。土木グループの酒井、髙尾及び金戸は、同打合せを経て、津波の想定水位を決めて対策工事の検討プロセスに移行するという認識であった。担当者らは、被告人武藤に対し、①津波の確率論的安全評価の手法について説明し、②沖合防波堤を設置し、既設防波堤を拡張した場合(ただし、工期及び施工の実現性は考慮されていない。)、4m盤の水位が1ないし2m程度低減され、その建設費が数百億円程度に上ること、③延宝房総沖地震津波の波源を用いた場合に水位を低減できる可能性があり、三陸沖とそれ以南の地震の発生様式について検討を実施中であること、④沖合防波堤の建設には種々の許認可申請が必要となり、意思決定から防波堤完成までに少なくとも約4年(環境影響評価が必要な場合は更に約3年)必要であること、⑤海溝沿いの津波に対する対応の在り方について原子力事業者間で統一されていないことなどを報告した。これに対し、被告人武藤は、「長期評価」における波源設定の信頼性に疑問がある以上、電力会社だけで判断するのではなく、専門家による審査を受ける必要があるとして、耐震バックチェックでは現行の津波評価技術によって津波評価を行いつつ、土木学会に太平洋側津波地震の扱いの研究を委託し、その結果が出れば、その結果に応じた必要な対策を取ること、このような方針について有識者に説明してその意見を確認することを指示した。この被告人武藤の指示に対し、打合せの参加者から異論は述べられなかった。
(5) 被告人武藤の指示を受けた後の土木グループの検討状況
ア 他の原子力事業者の担当者らに対しては、平成20年7月31日、酒井が、同月23日の打合せで説明していた対策工事の検討プロセスが変更された旨の一報を入れた上、同年8月6日、酒井、髙尾、金戸らが、耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り入れるという従前の方針を変更し、当面は津波評価技術によって津波評価を行うが、「長期評価」の見解は無視することができないので、土木学会に太平洋側津波地震の扱いの研究を委託して津波評価技術を改訂し、改訂までに可能な対策を随時進めるという方針とすることを報告し、その方針の是非について打合せを行った。東京電力のかかる方針については、後に日本原電社内で意見が出なかったわけではないものの、他の原子力事業者の担当者らは、これに賛成する旨の意見を述べた。
イ 東京電力は、平成20年7月31日、東電設計に対し、日本海溝寄りプレート間を活動域とする想定津波の断層モデルとして、延宝房総沖地震の断層モデルを追加して本件発電所の津波の検討を行うよう依頼した。東電設計は、想定モデル、すなわち、津波評価技術に示されていた延宝房総沖地震津波を対象津波とする基準断層モデルを、後記の茨城県独自の想定断層モデルと等価とするために北に80km延長させ、かつ、モーメントマグニチュードを若干切り上げてMw8.3とし、断層長さとすべり量をやや大きくしたものを、宮城県金華山沖から房総沖までのプレート間の領域に設定してパラメータスタディを実施し、朔望平均満潮位で計算したところ、本件発電所における最大津波高さが敷地南側でO.P.+13.552m、想定モデルを上記領域の南端に設定して同様の計算をしたところ、本件発電所における最大津波高さが敷地南側でO.P.+10.949mという計算結果を得た。金戸は、同年8月22日、久保から、これらの計算結果を伝えられ、その内容を酒井らに報告し、酒井は、計算結果の概要を吉田に報告した。
ウ 安中は、前記の原子力事業者らとの打合せを受けて、平成20年8月18日、髙尾らに対し、海溝付近が一括して「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」とまとめられていることは、地震動の評価においては影響が大きくないことからそうした扱いがあまり問題とならないが、少なくとも確率論的な津波の評価においては、影響の大きな領域であることから、より現実的な区分について検討する必要があるとした上で、日本海溝寄りの津波地震に関するロジックツリーの分岐案として、①これまでに発生した領域のみで発生する、②どこでも発生するが、北部に比べ南部の津波地震は小さい、③どこでも発生し、南部でも北部と同程度の津波地震が発生するという3つを設定する旨の報告書を提出した。
エ 保安院は、平成20年9月4日、東京電力を含む電気事業者等に対し、「新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項について」を発出して、耐震バックチェックの際に、新潟県中越沖地震により得られた知見を反映することを求めることとした。具体的には、地震動の評価に用いる震源モデルには不確かさが伴うことに留意する必要があるとされ、不確かさの考慮は、将来的には確率論的評価手法による結果も利用して実施することが考えられるが、現時点では、耐震設計審査指針においても確率論的評価手法による確率値は地震動等の判断基準として採用しておらず、超過確率を参照するという位置づけになっているため、不確かさを考慮して策定された基準地震動の超過確率を参照することとされた。
オ 平成20年9月7日、被告人武黒、同武藤、吉田、山下らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェック最終報告書の提出を1年強後ろ倒しして概ね平成22年度内で収めるべく調整中であることが報告された。
カ 髙尾らは、平成20年9月10日、電事連土木技術委員会において、原子力発電所の津波による水位評価の基準として津波評価技術が用いられているが、その後の調査、研究の進展等に基づき、地震本部や中央防災会議等から波源に関する新たな知見が示されていること、津波評価技術策定当時から数値計算技術が進歩していること等から、最新の知見・技術に照らして津波評価技術の改訂を行う必要があり、また、津波による波力評価、砂移動評価及び確率論的水位評価技術については、基準化まで至っておらず、将来の安全審査又はバックチェックの審議の円滑化を目的として、これらの技術の基準化を図る必要があるとして、合理的な波源モデルの提案及びこれらの技術の体系化を内容とする「津波評価技術の高度化研究(その2)」を、次年度における各電力会社共通の研究案件として提案し、了承された。その提案理由書には、緊急性(提案時期から開発する必要性)として、波源に関する新知見に基づく津波水位の上昇はプラント停止を求められるリスクがあり、直ちに実施する必要がある旨記載されており、研究期間としては、平成21年8月から平成24年3月までとされていた。同案件は、平成21年11月以降、土木学会津波評価部会において議論、審議されることとなった。
キ 金戸は、平成20年9月10日、本件発電所の所長らに対し、耐震バックチェック中間報告の概要や課題を説明した。その際、金戸は、配布資料に基づき、津波評価技術の示す津波波源に基づいて計算した本件発電所の最高水位はO.P.+5.7mであるが、「長期評価」は津波地震が海溝寄りのどこでも発生する可能性があるとしており、津波に関する学織経験者のこれまでの見解及び地震本部の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると、現状より大きな津波高を評価せざるを得ないと想定され、津波対策は不可避であることを説明した。
ク 髙尾らは、津波評価技術の高度化研究の開始に先立ち、平成20年10月中旬から下旬にかけて、土木学会津波評価部会の主査又は委員を務めかつその一部は保安院の審査にも関与している地震又は津波の専門家4名(首藤、佐竹東京大学教授、高橋智幸秋田大学准教授、今村)に対し、「長期評価」の見解について原子力発電所の津波評価という観点から土木学会において審議し、津波評価技術の改訂を行うこと、進行中の耐震バックチェックは現行の津波評価技術をベースに行うが、津波評価技術の改訂後、その改訂された津波評価技術に照らして安全性の評価をし直すことといった東京電力の方針を説明し、基本的な了解を得た。その際、上記4名の中に、津波評価技術の改訂を待つことなく直ちに津波対策を実施すべきであり、「長期評価」を踏まえた対策が取られるまで原子力発電所を停止すべきであるというような意見を述べる者はいなかった。なお、髙尾は、佐竹に説明をした際、同人から、堆積物調査に基づく貞観地震(869年に発生し、石巻平野や仙台平野に大きな津波被害をもたらし、当時、宮城県沖又はその周辺で発生したと考えられていた地震)による津波の波源モデルに関する論文の原稿を受領した。同論文には、「断層の南北方向の広がり(長さ)を調べるためには、仙台湾より北の岩手県あるいは南の福島県や茨城県での調査が必要である」と記載されていた(その後の平成22年に発表された行谷佑一ら執筆の論文にも、「石巻平野から請戸地区における津波堆積物を用いて貞観地震の断層モデルを検討したが、断層の南北の拡がり(長さ)などをさらに検討するために、今後、石巻平野よりも北の三陸海岸沿岸や、あるいは請戸地区よりも南の福島県、茨城県沿岸における津波堆積物の調査が必要である」と記載されていた。)。金戸は、平成20年10月頃以降、東電設計に対し、佐竹ら執筆の上記論文で想定することが適切とされた貞観地震津波の波源モデル(同論文におけるモデル8及び10)に基づく津波水位計算を依頼し、同年11月12日、本件発電所の取水口前面における朔望平均満潮位の最大津波高さがO.P.+9m前後となる旨の計算結果を受領した。
酒井、髙尾、金戸らは、平成20年11月13日、吉田に対し、上記の専門家4名への説明の結果を報告した。その際、酒井らは、貞観地震津波については、波源が確定していないことから、福島県南部の堆積物調査を行った上で土木学会に波源の検討を委ね、進行中の耐震バックチェックの津波評価では取り扱わないという方針で対応に当たることとした。
ケ 酒井、髙尾らは、平成20年12月10日、阿部に対しても、前記の東京電力の方針を説明し、一応の了解を得た。もっとも、その際、阿部からは、「長期評価」に対応する対策を取らないためには積極的な証拠が必要であり、福島県沿岸の津波堆積物調査を実施し、「長期評価」に対応する津波が過去に発生していないことを示してはどうかという意見が述べられた。その際、阿部も、津波評価技術の改訂を待つことなく直ちに津波対策を実施すべきであり、「長期評価」を踏まえた対策が取られるまで原子力発電所を停止すべきであるといった意見を述べることはなかった。
なお、髙尾らは、同月18日、吉田に対し、阿部への説明の結果を報告して、津波堆積物調査を実施することとし、同調査は、平成21年7月、東京電力においてその実施が承認され、同年12月から平成22年3月にかけて、実施された。
(6) 以上のとおり、被告人武藤は、平成20年6月10日、吉田らから、プレート間大地震(津波地震)が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとする「長期評価」が公表されたこと、これをロジックツリーの分岐の一つとして扱い、重み付けアンケートの結果、地震学者の平均で上記地震が上記領域内のどこでも発生するが0.6、福島県沖では発生しないが0.4であり、その結果を踏まえた6号機の津波ハザード曲線は、O.P.+10mの年超過確率が10のマイナス4乗と5乗の間、O.P.+13mの年超過確率が10のマイナス5乗と6乗の間であること、明治三陸地震モデルによるパラメータスタディの結果、最高津波水位がO.P.+15.7m、鉛直壁に当たる津波高さが最大O.P.+約20mになること、「長期評価」は耐震バックチェックに取り込まざるを得ないものの、明確な根拠が示されておらず信頼性がないことなど、本件発電所における津波水位評価の概況等について説明を受けた上、「長期評価」の扱いについて判断を求められたのに対し、同年7月31日、土木学会の検討に委ねてその結果に応じた対策を取る、耐震バックチェックの津波評価は現行の津波評価技術によって行う、こうした方針について有識者の了解を得るという方針を示し、土木グループは、この方針に従って、有識者の了解を取り付け、「長期評価」の扱いについて土木学会に研究を委託する手続を取り、有識者の了解を取り付ける過程で知った貞観地震の扱いについても、有識者の意見も踏まえて、堆積物調査を行った上で「長期評価」と併せて土木学会の検討に委ねることとした。この過程において、被告人武藤が示した方針に対し、東京電力社内はもとより、他の原子力事業者の担当者、さらには有識者からも、意見が全くなかったわけではないものの、最終的には異論が示されることはなかった。
11 平成21年2月11日開催の中越沖地震対応打合せ
平成21年2月11日、被告人ら3名、吉田、山下、酒井らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェックの状況が議題とされ、保安院から平成21年3月末までの全プラント中間報告の要請があったこと、本件発電所の5号機以外の中間報告を平成21年6月末までに行う方針であること、本件発電所の全号機の最終報告が平成24年11月末までとなる見込みであることが報告された。被告人勝俣が、耐震バックチェック最終報告の時期と対策工事完了の時期との関係を尋ねた際、山下が、バックチェックルール上、工事は後でもよいこととなっているが、最近はそうではない流れもある旨答えた。また、山下が、土木学会手法(すなわち津波評価技術)によっても、潮位データ及び海底地形データの更新により、本件発電所5号機及び6号機の津波水位が海水ポンプ位置で従前の評価値を上回るO.P.+6.1mとなることを説明し、これに続いて、吉田が、土木学会評価でかさ上げが必要となるのは、本件発電所5号機及び6号機の海水ポンプのみであるが、土木学会評価手法の使い方をよく考えて説明しなければならない、「もっと大きな14m程度の津波が来る可能性があるという人もいて」、前提条件となる津波をどう考えるか、そこから整理する必要がある旨述べた。
12 被告人武黒に対する平成21年4月ないし5月頃の吉田部長らによる東電設計の津波水位計算に関する報告
(1) 被告人武黒に対する報告
被告人武藤は、平成20年8月初旬頃、被告人武黒に対し、「長期評価」の概要、「長期評価」の見解に従って福島県沖の日本海溝沿いに津波の波源を置いて計算したところ、本件発電所で高い津波水位となったが、「長期評価」にはよく分からないところがあるので、土木学会に検討を依頼し、結果が出れば、その結果に応じた対策工事を行う方針であることを報告し、これに対して、被告人武黒は異論を述べなかった。
被告人武黒は、吉田に対し、平成21年2月11日の中越沖地震対応打合せにおける同人の前記の発言について説明を求め、同年4月又は5月頃、吉田から、「長期評価」が三陸沖から房総沖までの領域のどこでも津波地震が起きる可能性があるとしていること、「長期評価」の見解に基づいて明治三陸地震の波源モデルを福島県沖に設定すると本件発電所の最高津波水位が敷地南側でO.P.+15.7mとなること、「長期評価」は津波地震が海溝寄り領域内のどこでも起きるとする具体的な根拠を示していないこと、地震本部自ら海溝寄り領域のどこでも起きるとする点の信頼度を下から2番目のCクラスに分類していること、中央防災会議も「長期評価」の見解を採用していないこと、「長期評価」の取扱いについて土木学会に検討を依頼し、その検討には数年を要すること、以上の方針について主要な学者の了承を得ていることの説明を受けた。被告人武黒は、吉田に対し、見通しが立った段階で必要な対策を準備するよう指示した。また、被告人武黒は、同年6月頃、酒井からも改めて「長期評価」の概要について説明を受けるとともに、土木学会の検討に約3年を要することの説明を受けた。
(2) 被告人武黒に対する報告後の検討状況
ア 被告人武藤は、平成21年5月又は6月頃、同年6月25日開催の株主総会における原子力・立地本部本部長の手持資料に「巨大津波に関する新知見」として、「貞観津波に関する知見 宮城県沿岸の津波堆積物に関する調査結果から貞観津波の波源として2つのモデルが新たに提案されており、これに伴う津波を考慮すると福島第一、第二とも敷地レベルまで達し、非常用海水ポンプは水没する。」と記載されていたため、貞観地震について酒井に尋ね、モデルが確定していないため、「長期評価」の見解と併せて土木学会で審議されることとなっている旨の説明を受けた。
イ 東京電力は、平成21年6月19日、保安院に対し、本件発電所の1号機から4号機まで及び6号機における主要施設についての耐震安全性評価を加えた、本件発電所の耐震バックチェック中間報告書(改訂版)を提出した。同報告書には、地震随伴事象(津波に対する安全性、周辺斜面の安定性)については、現在解析・評価を行っているところであり、最終報告において結果を示す予定である旨記載されていた。
ウ 保安院は、作業部会を設置して本件発電所5号機の耐震バックチェック中間報告の内容について審議を行い、平成21年7月21日、策定された基準地震動Ssは妥当なものであり、建物・構築物(原子炉建屋)及び機器・配管系は基準地震動Ssに対しても耐震安全性が確保されている旨の評価書を公表した。これに先立つ同年6月24日、上記作業部会において、地質、活断層関係の専門家(産業総合研究所の岡村行信)が、中間報告がプレート間地震として貞観地震に全く触れていないのは納得できない旨指摘していた。この指摘を受けて、保安院は、佐竹らの前記論文に基づいて貞観地震の津波評価における波源モデルを震源断層と仮定して地震動評価を実施したところ、上記中間報告がプレート間地震を考慮して策定した基準地震動を下回ることを確認し、その旨を評価書に記載するとともに、貞観地震については、津波堆積物や津波の波源等に関する調査研究が行われていることを踏まえ、今後、事業者が津波評価及び地震動評価の観点から、適宜、当該調査研究の成果に応じた適切な対応を取るべきである旨を記載した。酒井は、同年6月24日、被告人武黒らに対し、耐震バックチェック中間報告の審議において、上記のとおり貞観地震に関する指摘があったことを報告したが、その際、耐震バックチェック最終報告で貞観地震津波に対応するとなると設備対策が間に合わない旨のコメントを付していた。
エ 平成21年6月28日、被告人ら3名、吉田、山下らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェックの状況が議題とされた。その際、被告人勝俣が、福島の耐震補強工事が完成するのはいつになるのか、解析は平成23年に完了しているのに、補強工事が遅れると説明が難しいのではないかと尋ね、山下が、解析の報告と同時に補強工事も完了させたいが、柏崎刈羽に解析員を総動員している、バックチェックが完了した時点で補強工事が完了しているのが望ましい旨述べた。
オ 髙尾は、津波評価技術が改訂されて設計津波水位が見直され、津波対策工事が必要となった場合に備えて、予め検討を進めておく必要があると考えたことから、平成21年6月末頃、酒井に対し、津波対策工事の円滑な検討を行うために、津波水位評価を行う土木グループと安全性評価、対策工事の検討を行う複数グループとを取りまとめる会議体を設置することを進言し、酒井が関係グループに掛け合ったものの、同年7月、そのような会議体は不要であるとされた。
カ 酒井、髙尾及び金戸は、平成21年8月28日、保安院の名倉繁樹審査官のヒアリングを受け、貞観地震津波への対応について、津波堆積物調査を実施中であり、波源の合理的設定は土木学会で検討すること、耐震バックチェック最終報告には間に合わないが、合理的に設定された波源に対し必要な対策を実施していくこと、以上の方針について有識者の了解が得られていることなどを説明した。これに対し、名倉審査官は、個人的には、耐震バックチェックは確立された土木学会ベース(すなわち津波評価技術)で行い、貞観地震津波に対しては研究の進展で余裕の確保の観点から自主保安として対策を実施するという扱いでよいと思う旨述べた。酒井は、同日、吉田、山下らに対し、上記ヒアリングの内容を報告した。
キ 平成21年9月6日、被告人ら3名、吉田、山下らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、本件発電所及び福島第二原子力発電所の耐震バックチェックの状況が議題とされた。その際、耐震補強工事に関し、被告人勝俣が、まずは補強工事ができるところから進めていくしかない、これは投資なので早めにやればよい旨述べた。
ク 酒井、髙尾及び金戸は、平成21年9月7日、保安院の小林勝耐震室長及び名倉審査官に対し、貞観地震津波への対応について、改めて前同様に説明するとともに、貞観地震津波の波源モデルに基づく津波水位の解析結果を報告した。小林及び名倉から、東京電力の対応方針に対して特段の異論は述べられず、また、保安院側の専門家においても、貞観地震津波を耐震バックチェックの基本ケースで扱う必要はないが、何らかの形で安全性に言及できるのが理想と考えている旨の指摘があった。
ケ 前記のとおり、東京電力は、東電設計に対し、津波ハザード解析を委託していたところ、平成22年5月12日、土木グループの髙尾、金戸らは、東電設計の安中らから、貞観地震津波による堆積物調査の成果等も踏まえた解析結果の概要の報告を受け、福島地点におけるハザード曲線を示された。そのハザード曲線は、津波高さ10mの年発生頻度がフラクタイル算術平均で10のマイナス4乗よりもやや低い頻度というものであった。
コ 髙尾は、平成22年7月に土木グループのグループマネージャーに昇格した後、津波評価技術の改訂に対応した対策工事の円滑な検討を行うために複数グループを取りまとめる前記の会議体の設置を再度進言し、同年8月27日以降、設計津波水位に対する対策工事を検討する会議体として、対策センター長(当時、土方勝一郎)、土木グループ、対策工事の担当グループからなる福島地点津波対策ワーキング(以下「津波対策ワーキング」という。)が開催されるようになった。
(3) 以上のとおり、被告人武黒は、被告人武藤及び吉田から、「長期評価」の見解に基づくと本件発電所の最高津波水位がO.P.+15.7mとなるが、「長期評価」の見解は、具体的な根拠を示しておらず、地震本部自らも信頼度をCに分類しており、中央防災会議も採用していないこと、その扱いについて土木学会に検討を依頼しており、その検討に数年を要し、そのような方針について主要な学者の了承を得ていることなどについて説明を受けた。他方、本件発電所5号機の耐震バックチェック中間報告の審議の過程において、貞観地震津波の取扱いが問題となって、今後、調査研究を踏まえた適切な対応を取るべきであるとされたものの、それ以上に問題視されることはなく、このような経緯についても被告人武黒らに報告されたが、貞観地震津波は土木学会で検討し、耐震バックチェック最終報告は津波評価技術に基づいて行うなどとする方針について、保安院側から異論が示されることはなかった。
13 土木学会第4期津波評価部会における議論
(1) 平成22年12月7日、土木学会第4期津波評価部会が開催され、髙尾が委員として、金戸が幹事としてそれぞれ出席した。同部会では、最新知見を踏まえた津波評価技術の改訂、津波による波力、砂移動評価手法の基準化、確率論的水位評価の標準的な手法の提示を研究目的として、波源モデルに関する検討、数値計算手法に関する検討、不確かさの考慮に関する検討、津波評価技術の基準化・標準化の研究に取り組んでいた。同日の部会では、幹事団が、配布資料「波源モデルに関する検討~日本海溝沿い海域の波源域について~」に基づいて、三陸沖から房総沖にかけての日本海溝寄りのプレート間大地震の波源モデルを提案した。同資料には、三陸沖から房総沖海溝寄りのプレート間大地震について、北部と南部を分割し、各活動域内のどこでも津波地震は発生するが、北部領域に比べ南部ではすべり量が小さく、南部は延宝房総沖地震津波を参考に波源モデルを設定する旨記載されていたが、幹事団のこの提案に対し、異論は述べられなかった。
(2) 平成23年1月13日、土方、金戸ら津波対策に関係するグループの担当者らが出席して津波対策ワーキングが開催され、金戸は、上記の土木学会津波評価部会における審議経過として、幹事団が、「長期評価」の見解に対応した波源として、日本海溝南部では延宝房総沖地震津波の波源を用いることを提案したところ、この提案に異論がなかったこと、この提案に従った場合でも想定される津波が10m盤を超えて襲来してタービン建屋等が浸水する可能性があることを報告した。
なお、同年2月6日、被告人ら3名、清水正孝(社長)、吉田(本件発電所所長)、山下(原子力設備管理部長)、土方(対策センター長)らが出席して中越沖地震対応打合せが開催され、福島地区における耐震裕度向上工事について説明があり、本件発電所の耐震バックチェック最終報告書の提出が平成28年3月となる見込みであることが報告された。また、最終報告書の提出時期と耐震裕度工事の完了時期の関係が議論され、清水が、報告書の提出が工事完了後になるのかと尋ねたのに対し、被告人武藤が、工事が完了した状態で最終報告書を提出するのが暗黙のルールとなっている旨を、続けて、吉田が、対外的説明のしやすさも考えると工事を完了してセットで報告書を提出する旨をそれぞれ説明した。同打合せで配布された資料には、耐震裕度向上工事の概略を説明する表の末尾に「地震随伴事象の津波対策は、津波高さが決定していないため、対策内容、工事費用は未確定」と記載されていた。
(3) 平成23年2月14日、土方、髙尾ら津波対策に関係するグループの担当者らが出席して津波対策ワーキングが開催され、土木グループから、延宝房総沖地震津波の波源を設定した場合、津波の遡上により本件発電所のタービン建屋及び原子炉建屋が浸水する可能性があること、津波対策工事(防波堤かさ上げ、防潮堤構築)を実施しても、浸水を全て食い止めることはできないことが報告された。同日配布された資料には、津波対策工事に関する検討として、本件発電所の1号機から4号機までの前面護岸並びに5号機及び6号機の前面護岸を囲う形で防潮堤を設置した図面が記載され、その成立性(効果、コスト、工期など)を概略評価する計画である旨も記載されていた。
(4) 保安院の名倉は、平成23年2月22日、地震本部との情報交換会において、地震本部が同年4月に太平洋側プレート境界の地震に関する「長期評価」改訂版を公表し、その中で貞観地震に言及する予定である旨の情報に接し、同日、髙尾を呼び出して、東京電力の貞観地震津波への対応状況を尋ね.「長期評価」改訂版の内容次第では、事業者に対し耐震バックチェック最終報告へ向けて何らかの指示を出す可能性がある旨告げた。髙尾らは、山下と土方の了解を得た上で、同年3月7日、保安院の小林、名倉らに対し、津波対策について、土木学会津波評価部会における審議状況や貞観地震津波を視野に入れて社内で検討中であること、津波評価について、平成24年10月と見込まれていた津波評価技術の改訂時期や耐震バックチェック最終報告の時期に応じて対応すること、津波対策の検討状況として、津波対策工事(防波堤・護岸の強化、建物・構築物の新設、ポンプの水密化等)に関する検討や津波対策工事を考慮した津波評価の合理化に関する検討を行っているが、平成24年10月までに津波対策工事を完了することは無理であること、津波波源に関する検討状況として、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りプレート間大地震(津波地震)について、北部は明治三陸地震、南部は延宝房総沖地震を参考に波源を設定すること、福島県沖に明治三陸地震を参考に波源を設定すると津波水位が最高O.P.+15.7mとなり、延宝房総沖地震を参考に波源を設定すると津波水位が最高O.P.+13.6mとなること、貞観地震津波について、断層モデルの成熟度が低く、津波評価技術の改訂には取り込まれない見込みであることを説明した。これに対し、名倉から、耐震バックチェックの審議中に津波評価技術の改訂があり、対策が完了していないと即アウト(耐震バックチェックの審議の停止を意味すると解される。)になりかねないこと、地震本部による「長期評価」改訂の公表内容や他の事業者の耐震バックチェックの審議状況によっては、保安院から東京電力に指示を出すこともあり得ることが指摘されたが、その際、保安院側から「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施すべきであり、その対策工事が終わるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるというような指摘がされることはなかった。髙尾は、平成23年3月7日、被告人武藤らに対し、保安院からのヒアリングの結果を、保安院の「コメントから、津波対策工の検討を着実に実施する必要がありますので、社内津波WG事務局と相談して進めたいと思います」とのコメントを付して、電子メールで報告した。
(5) 平成23年3月2日、土木学会第4期津波評価部会が開催された。同日の部会では、三陸沖から房総沖にかけての日本海溝寄りのプレート間大地震について、北部と南部を分割し、南部は延宝房総沖地震津波を参考に波源モデルを設定することを前提に波源モデルに関する詳細な検討が行われた。また、従前の津波評価技術が断層面のどこでも同じようにすべると仮定した均質すべりの断層モデルを基本とした体系であったのに対し、同部会では、アスペリティの面積比、すべり量比を模式化したアスペリティモデルを採用した場合の想定津波の評価手法について検討することとされていたが、同日の時点では、その評価手法については未だ審議の途上であり、一定の結論が出るには至っていなかった。
(6) 以上のように、土木学会第4期津波評価部会では、平成22年12月、海溝寄り領域の南部(すなわち福島県沖を含む。)では延宝房総沖地震津波を参考に波源モデルを設定するということ自体については異論がなかったものの、平成23年3月初旬の時点においても、その具体的な波源モデルや数値計算の手法については未だ審議の途上にあった。また、保安院の担当者は、O.P.+15.7m又はO.P.+13.6mという明治三陸地震又は延宝房総沖地震を参考に福島県沖に波源を設定した場合における本件発電所の最高津波水位を知らされ、津波評価技術の改訂と耐震バックチェック最終報告との時期の関係次第では、対策工事完了の有無が問題となる旨の指摘はしたものの、「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施し、工事完了までは本件発電所の運転を停止すべきであるといった指摘をすることはなかった。
そして、被告人ら3名は、本件地震発生前、上記のような土木学会津波評価部会における審議の状況を知らず、土木グループの担当者などに対し、審議の状況の報告を求めたこともなかった。
14 小括
以上に概観したとおり、原子炉の設置、運転に関しては、原子炉の危険性に鑑み、法令上、その設置等に許可を必要とし、設置後も一定の基準の維持が求められていたことに加え、政府には原子力に関する安全性確保のための専門機関が設けられ、各機関において原子炉の安全性確保ための規制や指針等の策定、これらに基づく原子力事業者の監督、審査が行われるなど、その安全性確保は国にとって重要事項として位置付けられていた。そして、原子力事業者には、法令上の義務又は自主的な対策として、国の示す安全性確保のための指針等に従い、日頃から新しい技術や知見に関する情報の収集及び分析を行うとともに、必要に応じてこれらを安全対策の基礎として取り入れることによって、原子炉による災害のリスクを常に最大限低減したレベルでの安全性確保が求められていたといえる。
そのような中で、東京電力は、本件発電所について、法令上の許可を得た上で設置、運転していたことは勿論、安全対策の面でも、地震及び津波に対する原子炉の安全性確保のための指針等の策定、改訂等があった際や、地震又は津波に関する新たな知見が示された際には、必要に応じて適宜社内の担当部署で検討を行い、行政機関からの求めに応じて報告等を行うなどしてきたものと認められる。また、東京電力は、これらの検討に当たり、社内で調査、検討するだけでなく、他の原子力事業者との情報交換、関連分野に精通した研究者を含む複数の専門家からの意見聴取等により、外部の意見を収集し、これらを踏まえて会社としての方針を決め、最終的には監督、審査を行う行政機関側の考えも踏まえた上で、必要と判断される対応を進めていた。このように、本件発電所は、地震及び津波に対する安全性を備えた施設として、適法に設置、運転されてきたものである。そして、地震本部から、福島県沖を含む海構寄り領域のどこでもMt8を超える明治三陸地震クラスのプレート間大地震(津波地震)が発生する可能性がある旨の「長期評価」が公表され、これを踏まえた津波ハザード解析によれば、O.P.+10mの津波の年超過確率が10のマイナス4乗と5乗の間の頻度、O.P.+13mの津波の年超過確率が10のマイナス5乗と6乗の間の頻度となり、また、パラメータスタディを実施した結果、津波最高水位がO.P.+15.7m、鉛直壁に当たる津波高さが最大O.P.+約20mになるといった情報があり、本件地震発生前、津波水位評価の業務に当たっていた東京電力土木グループの酒井、髙尾及び金戸のいずれも、「長期評価」の見解を耐震バックチェックに取り込まざるを得ず、それを踏まえた対策工事も進めていかなければならないと考えてはいたものの、本件発電所の安全性が確保されておらず、「長期評価」を踏まえた対策を講じるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるとは考えておらず、また、関東以北の太平洋岸に原子力発電所を設置、保有する他の原子力事業者が、「長期評価」を踏まえた津波対策を講じるまで原子力発電所の運転を停止することを検討していたことも窺えない。さらに、東京電力の取ってきた本件発電所の安全対策に関する方針や対応について、行政機関や専門家を含め、東京電力の外部からこれを明確に否定したり、再考を促したりする意見が出たという事実も窺われない。
もっとも、東京電力は、耐震バックチェックがそうであったように、原子炉の安全対策に関しては、当時の最新の科学的知見を取り入れた上で行うことが求められていた中で、「長期評価」の見解に対しては、土木グループを中心として継続的に検討こそしていたものの、その信頼性には疑義があるとして、これを直ちに安全対策に取り入れるには至らなかった。この点、指定弁護士は、「長期評価」を本件において予見可能性を肯定する上での重要な知見と位置付けているのに対し、弁護人らは、「長期評価」には信頼性、成熟性がなく、被告人ら3名に予見可能性を生じさせるものではなかった旨主張している。前記認定の一連の事実経過に照らしても、10m盤を超える津波襲来の可能性に関する情報として被告人らが接したものは、Mt8を超える明治三陸地震クラスのプレート間大地震(津波地震)が三陸沖北部から房総沖の海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性がある旨の「長期評価」の見解であり、これを前提に数値解析が行われた前記の津波ハザード、解析及びパラメータスタディであったのであり、被告人ら3名の予見可能性を検討する上では、「長期評価」が決定的に重要な意味を持っていたというべきである。そこで、次に、平成23年3月初旬の時点における「長期評価」の信頼性について検討を加えることとする。
第6 「長期評価」の信頼性
1 「長期評価」の内容
「長期評価」は、前記のとおり、三陸沖から房総沖までの領域を8つに分け、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りを一つの領域(海溝寄り領域)とした上で、同領域におけるプレート間大地震(津波地震)について、明治三陸地震と同様のMt8.2前後の地震が領域内のどこでも発生する可能性があり、今後30年以内の発生確率は20%程度であることなどを内容とするものである。改めて、その内容をやや詳細にみると、以下のとおりである。
「長期評価」は、三陸沖から房総沖までの領域を8つに分け、三陸沖北部から房総沖の海溝寄り(南北約800km、東西約70km)を一つの海溝寄り領域とした上で、同領域におけるプレート間大地震(津波地震)に関し、まず、過去の地震について、「M8クラスの地震は17世紀以降では、1611年の三陸沖、1677年11月の房総沖、明治三陸地震と称される1896年の三陸沖(中部海溝寄り)が知られており、津波等により大きな被害をもたらした。よって、三陸沖北部~房総沖全体では同様の地震が約400年に3回発生しているとすると、133年に1回程度、M8クラスの地震が起こったと考えられる。これらの地震は、同じ場所で繰り返し発生しているとは言いがたいため、固有地震としては扱わなかった。」と評価し、震源域の形態の特性について、「陸側のプレートと太平洋プレートの境界面。低角逆断層型。」、震源域の特性について、「日本海溝に沿って長さ200km程度の長さ 幅50km程度の幅。具体的な地域は特定できない。」、その根拠について、「震源域は、1896年の「明治三陸地震」についてのモデル(中略)を参考にし、同様の地震は三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があると考えた。」、発生間隔等の特性について、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り全域 平均発生頻度 400年に3回程度」、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのうち特定の200kmの領域 平均発生頻度 530年に1回程度」と評価した。これらを踏まえ、同領域における次の地震の発生時期及び規模について、「M8クラスのプレート間の大地震は、過去400年間に3回発生していることから、この領域全体では約133年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定される。ポアソン過程により、今後30年以内の発生確率は20%程度、今後50年以内の発生確率は30%程度と推定される。また、特定の海域では、断層長(200km程度)と領域全体の長さ(800km程度)の比を考慮して530年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定される。ポアソン過程により、今後30年以内の発生確率は6%程度、今後50年以内の発生確率は9%程度と推定される。次の地震も津波地震であることを想定し、その規模は、過去に発生した地震のMt等を参考にして、Mt8.2前後と推定される。」と評価し、その発生確率等を示した表には「次の地震の規模」の欄に「Mt8.2前後」、備考欄に「約400年間に顕著な津波を伴った大地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りに3回発生していると判断し、平均発生間隔を133.3年(=400年/3回)とし、ポアソン過程により三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのどこかで発生する確率を算出した。また、1896年の地震の断層長が三陸沖北部から房総沖の海溝寄り全体の0.25倍程度を占めることから、特定の海域では同様の地震が530年に1回発生するものとして、ポアソン過程から発生確率を算出した。」と記載されていた。
なお、固有地震とは、その領域内で繰り返し発生する最大規模の地震である。Mとは、地震波(地震動)の大きさ(揺れの大きさ)の分布を使って算出する地震の規模を表すマグニチュードであり、Mtとは、前記のとおり、津波マグニチュードのことであり、津波の高さの分布を使って算出する地震の大きさの指標である。ポアソン過程とは、過去に起きた頻度のみから発生確率を予測する手法であり、ポアソン過程を用いた場合、地震発生の確率はいつの時点でも同じ値となり、本来時間とともに変化する確率の平均的なものとなる。
2 作成主体、作成過程
「長期評価」を策定・公表した地震本部は、平成7年1月に兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)が発生した後、地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制になっていなかったという課題意識の下に、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし、これを政府として一元的に推進するため、同年、地震防災対策特別措置法に基づき総理府(後に文部科学省)に設置された政府の特別機関であり、地震防災対策の強化、特に地震による被害の軽減に資する地震調査研究の推進を基本的な目標としている。地震本部には、地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行う事務を行う地震調査委員会(平成14年当時、阿部が委員長代理を務め、島崎らが委員を務めていた。)が設置され、その下に、主要な活断層帯で発生する地震や海溝型地震を対象に、様々な調査・研究で得られた成果を利用して、地震の発生した位置、発生間隔、直近に発生した時期、次の地震の発生可能性を評価する長期評価部会(平成14年当時、島崎が部会長を務め、都司ら多数の地震等の専門家が委員を務めていた。)が設置され、同部会で審議される海溝型地震に関する審議を行う場として海溝型分科会(平成14年当時、島崎が主査を務め、阿部、佐竹及び都司ら多数の地震等の専門家が委員を務めていた。)が設置されていた。地震本部は、平成11年4月23日、「地震調査研究の推進について-地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」を決定し、この中において、「全国を概観した地震動予測地図」の作成を当面推進すべき地震調査研究の主要な課題とし、また、「陸域の浅い地震、あるいは、海溝型地震の発生可能性の長期的な確率評価を行う」としていたところ、海溝型分科会、長期評価部会、地震調査委員会における各審議を経て、平成14年7月31日に公表された「長期評価」は、三陸沖から房総沖までの領域を対象とし、長期的な観点で地震発生の可能性、震源域の形態等について評価して取りまとめたものである。
このように、「長期評価」は、地震に関する調査研究の推進を基本的な目標とする政府の特別機関である地震本部において、海溝型分科会、長期評価部会、地震調査委員会という階層的な会合において地震等に関する多数の専門家らによる議論を経て、異論等も検討した上で取りまとめられたものである。
3 評価方法、審議経過
もっとも、「長期評価」は、過去の地震を評価した上で次の地震の発生時期や規模を評価するというものであって、領域によって過去の地震のデータの質及び量は様々であり、これに伴い評価方法にも様々なものが混在しているから、その信頼性は領域によって異なるとみるほかない。このことは、後記のとおり、後に地震本部自らが領域ごとに評価の信頼度をランク付けしていることからも明らかというべきである。また、保安院は、平成21年5月に内規、いわゆる「新知見ルール」を定め、報告を受けた科学的、技術的知見について、これを整理した上、耐震安全性評価に反映させるべき新知見に該当するか否かを規制当局として判断することとしたが、同年3月9日に公表された「長期評価」の改訂版について、耐震安全性の評価及び耐震裕度への反映が必要な「新知見情報」又は耐震安全性の再評価や耐震裕度の評価変更につながる可能性のある「新知見関連情報」とは扱わず、耐震安全性評価に関連する「参考情報」として扱っているところである。さらに「長期評価」の海溝寄り領域に関する審議経過をみると、過去の地震のデータがない又は少ないためよく分からない所については、震源の特定よりも津波被害に対する警告を優先させ、たとえ仮置きであっても何らかの数字を示すべきであるとの考慮が働いたと考えられる場面も見受けられる。「長期評価」は、上記のような評価方法により、このような審議経過を経て策定されたものであるから、その信頼性を判断するに当たっては、作成主体や作成過程のみならず、その内容を具体的に考察する必要がある。
4 過去の地震の評価
「長期評価」は、1896年の明治三陸地震、1611年の慶長三陸地震及び1677年の延宝房総沖地震が、いずれも日本海溝寄りで発生した津波地震であると評価している。このうち1896年の明治三陸地震については、本件地震発生当時、地震学者の間において、日本海溝寄りで発生した津波地震であるとの考えが通用していたものと認められる。これに対し、1611年の慶長三陸地震については、長期評価部会海溝型分科会における審議経過や文献によれば、本件地震発生当時、地震学者の間において、千島沖の地震とする見解や正断層型地震とする見解、更には海底地すべりとする見解があったものの、この地震が日本海溝寄りで発生した(断層運動が直接の原因で生じた)津波地震であるとの見解が一定程度は通用していたものと認められる。また、1677年の延宝房総沖地震については、同分科会における審議経過や文献によれば、本件地震発生当時、地震学者の間において、陸に近い地震であったとする見解や、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震であったとする見解はあったものの、この地震が少なくとも日本海溝寄りで発生した津波地震であるとの見解が通用していたものと認められる。したがって、「長期評価」がこれら3つの地震をいずれも日本海溝寄りで発生した津波地震であると評価したことは、不合理とはいえない。
5 一つの領域として評価したことについて
「長期評価」は、地震の発生位置及び震源域の評価に当たっては、過去の震源モデルを参照し、微小地震等に基づくプレート境界面の推定に関する調査研究成果及び当該地域の速度構造についての調査研究成果を参照して領域を推定している。各領域の区域分けについては、微小地震の震央分布を参照し、過去の大地震の震央、波源域、震源モデルの分布、バックスリップモデルの研究成果を考慮している。このうち海溝沿いの領域については、明治三陸地震、1933年の三陸地震の震源モデルの幅と傾斜角から、海溝軸から約70km程度西側のところまでとしている。プレート境界の形状については、等深線や海底下構造調査の解析結果等を参照している。そして、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)について、過去に知られている慶長三陸地震及び明治三陸地震は、津波数値計算等から得られた震源モデルから、海溝軸付近に位置することが判っており、これからおよその断層の長さは約200km、幅は約50kmとし、南北に伸びる海溝に沿って位置すると考えたものの、過去の同様の地震の発生例は少なく、このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震であるとは断定できないため、同じ構造をもつプレート境界の海溝付近に同様に発生する可能性があるとし、場所は特定できないとしている。
津波地震が海溝軸近傍のプレート境界で発生することは確立した知見であるところ(甲A42(谷岡勇市郎・佐竹健治、平成15年、))「長期評価」の海溝寄り領域は日本海溝の海溝軸近傍のプレート境界にあり、プレートの沈み込み帯であるという点ではどこでも同じである。また、津波地震は、地震波の周波数が低く、周期の長い低周波地震の一種であるところ、海溝寄り領域では日本海溝から西側50ないし70kmまでの範囲内で低周波地震が発生している(甲A231(深尾良夫・神定健二、昭和55年)、247(渡辺偉夫、平成15年))。こうした海溝寄り領域の共通性は、「長期評価」を支える根拠となり得るものとはいえる。
しかしながら、海溝寄り領域を海溝方位が変化する北緯38.1度付近を境に北側領域と福島県沖を含む南側領域に分けた場合、両者は海底地殻構造が異なっている。すなわち、北側領域では、海洋プレートに海溝軸に平行して等間隔で隔てられた地形的起伏(ホルスト・グラーベン構造)が発達し、前弧領域はなめらかな地形であり、太平洋プレートと陸のプレートのバックストップ境界面との間には楔状堆積ユニット(付加体)が存在するのに対し、南側領域では、地形が不規則であり、周囲の海底から数キロメートル盛り上がる孤立した海山が存在し、前弧領域の海底の地形は複雑な構造的特徴を有しており、プレート境界には楔状堆積ユニットは見られず、ほぼ一定の厚みを持つ堆積ユニットが陸側のプレートと海洋プレートとの間の奥まで広がっているという違いがあり、また、プレート境界のカップリングも、深さが10ないし13kmを超える領域では、北側領域の方が南側領域よりもカップリングが強いという違いがある(弁104(鶴哲郎ほか、平成14年)、119(谷岡勇市郎ほか、平成9年)、120(松澤暢ほか、平成9年)、121(鶴哲郎ほか、平成12年)、122(鶴哲郎ほか、平成16年)、161(西澤あずさ、平成11年))。そして、津波地震の発生様式については、本件地震発生当時、その全体像が明らかにされるには至っていなかったものの、海溝軸近傍に堆積物(付加体)が存在し、この付加体を断ち切るように高角の分岐断層が動くこと、付加体の未固結の堆積物が跳ね上がること、付加体の剛性率が低いためすべり量が大きくなること、これらが海底地殻変動の上下成分を増加させて津波を隆起することが指摘されていた(甲A42(谷岡勇市郎・佐竹健治、平成15年)、弁28(谷岡勇市郎・佐竹健治、平成8年)、103(谷岡勇市郎・瀬野徹三、平成13年))。津波地震の中には中南米で発生した1960年のペルー地震や1992年のニカラグア地震のように付加体を形成していない又は大規模な付加体の存在が報告されていない領域を津波波源とするものもあるが(甲A42(今村文彦、平成15年))、上記のように付加体が津波地震の発生に影響を与えていることを指摘する知見は、平成15年当時の研究で大勢を占めており(甲A42(阿部勝征、平成15年))、本件地震発生当時においても津波地震を説明する代表的なモデルであり(弁102(谷岡勇市郎、平成21年))、付加体の存在と津波地震の発生が関連していることは地震学者の間で広く共有されていた(甲A42(松澤暢・内田直希、平成15年))。そうすると、明治三陸地震と同様のMt8.2前後の地震が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとした「長期評価」の見解は、付加体の存在が津波地震の発生様式と関連していると考えられていたことに照らせば、同領域における北側領域と南側領域との海底地殻構造の違いとは整合していなかったものといわざるを得ない。それにもかかわらず、「長期評価」は、平成21年3月9日に公表された一部改訂版を含め、この点に対する応答を示していなかったのであるから、Mt8.2前後の津波地震が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとしたことについて、本件地震発生前の時点においては、十分な根拠を示していたとはいい難い。
6 専門家らの評価
「長期評価」の策定に関わった島崎は、公判において、過去400年の間に海溝寄り領域の福島県沖で津波地震が起きた記録がないということは、地震の繰り返し間隔が長いことを示す情報であって、海溝寄り領域に地震が起きないことを示すものではないとし、過去に津波地震の発生が確認されていない地域を含めてどこでも地震が起こり得るとした「長期評価」の見解は合理的であったという趣旨の供述をしている。これに対し、同じく「長期評価」の策定に関わった阿部は、過去に津波地震の発生が確認されていない福島県沖や茨城県沖の海溝沿いの領域も含めて津波地震が発生する可能性があるとする点で、従来の地震予測に関する考え方からすると、非常に特異な評価である、過去の地震の発生状況や発生場所が明らかでなく、データ量自体乏しいことから、積極的に福島県沖などの領域で津波地震が発生するという立場は取っておらず、「そういう見方もあるのだな」という思いでいた旨供述し、地震本部事務局の立場で「長期評価」の策定に関わった文部科学省の地震調査管理官であった前田憲二も、海溝沿いの地震を必ずしも分かっていない領域も含めて全て一まとめにするというのは、少し乱暴な評価の可能性もあると思った、津波地震が海溝寄りでどこでも起こるという知見は特定の文献とか研究成果に基づくものではなかったと思う旨供述している。また、本件事故後に地震本部の地震調査委員会委員に就任した今村は、「長期評価」の見解には非常に違和感があり、同じ条件でどこでも発生するという根拠は分からなかった旨、地震学の専門家である松澤暢東北大学教授は、海溝寄りの領域を一括りにして評価をしたことは非常に乱暴な議論だと思った、理学的に正しいとは思わなかったが、現実的な解として仮置きの数字として示すしかないと考えた旨、地震学の専門家である大竹政和東北大学教授は、「長期評価」が相当の不確実さを持つ評価結果である旨、それぞれ述べているところである。これらの専門家らの評価は、「長期評価」の手法や見解には多かれ少なかれ無条件には賛同し難い点があることを示すものといえ、本件地震発生前の時点において、津波地震が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとしたことの根拠については、十分ではないという見方が複数の専門家の間にあったものと認められる。
確かに、前記のとおり、平成16年に土木学会津波評価部会が実施した重み付けアンケートにおける地震学者ら6名の回答の平均は、日本海溝寄り津波地震について、①過去に発生例がある三陸沖及び房総沖は活動的だが、発生例のない福島県沖は活動的でないとする見解に0.4、②これらは一体の活動域で、活動域内のどこでも津波地震が発生するとする見解に0.6の重みを付けており、地震学者の多くが「長期評価」の見解を支持しているかのように見える。しかし、このアンケートは、津波についての確率論的安全評価を検討する際に、認識論的不確かさのある事柄について、専門家の意見分布を把握することを目的として実施されたものであって、意見分布を客観的に評価するためには、各専門家が認織しているデータを共有し、専門家同土で議論をすることが有益と考えられるが、同アンケートは、このような過程を経たものではない。また、「長期評価」の策定に関わった2名の地震学者が①に0、②に1の重みを付けており、アンケートの趣旨が専門家の意見分布の集約なのか、個人の意見の表明なのかが必ずしも明らかにされないまま、アンケートが実施された疑いが残る。そうすると、上記のアンケート結果の平均値の評価には自ずと限界があり、「長期評価」の信頼性を判断するに当たってもあまり意味を持たないというべきである。
また、前記のとおり、酒井らが発表したマイアミ論文も、「日本海溝沿いのすべての領域において津波地震が発生すると仮定できる可能性がある。」と記載されているものの、そのような可能性を認識論的不確定性が存在する問題におけるロジックツリーの分岐の一つとして取り上げているにすぎないことが明らかであって「長期評価」の見解を取り込んでいるとはいえない。
さらに、指定弁護士は、前記の4省庁報告書が、既往の津波地震が確認されていなかった福島県沖に延宝房総沖地震及び明治三陸地震に基づく波源モデルを設定しており、「長期評価」の信頼性を裏付けている旨主張するが、4省庁報告書は、前記のとおり、想定地震を設定するに当たり、その発生位置を太平洋沿岸を網羅するように設定しつつ、三陸沖(G2)と福島県沖から房総沖まで(G3)とを別の領域に区分しており、福島県沖に明治三陸地震の波源モデルを設定してはいないのであるから、「長期評価」の見解と同じというわけではない。
7 公表前後の経緯
内閣府の担当者は、平成14年7月、公表予定の「長期評価」の内容を知り、地震本部事務局の前田に対し、情報の信頼度や精粗につき区別することなく公表することは問題が大きく、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)について、極めて少ない情報量でポアソン過程の手法により次の地震の発生確率を計算することには無理があり、また、実際に地震が発生していない領域で同様の地震の発生があるか否かを保証できず、防災対策を考えるに当たり、こうした確固としていないものについて、多大な投資をすべきか否か等については慎重な議論が不可欠であることを指摘して、地震本部に設置された政策委員会の検討を経た上で公表するか、やむを得ず公表する場合は、評価結果には相当の誤差を含んでいる旨を表紙に記載するよう申し入れた。そこで、協議の末、「長期評価」の表紙に「なお、今回の評価は、現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行ったものではあるが、データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから、評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり、防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要がある。」との記載が追加されることとなった。このような経緯は、内閣府の担当者からの申入れが主に財政的な観点からなされたものであったとしても、本件地震発生前の時点において、「長期評価」の信頼性に限界があったことを示しているということができる。
また、地震本部地震調査委員会は、平成15年3月24日、「千島海溝沿いの地震活動の長期評価について」を公表し、その際、「評価に用いられたデータは量及び質において一様ではなく、そのためにそれぞれの評価の結果についても精粗がある。」として、それまでに公表した評価の信頼度(地震発生の切迫度を表すものではなく、確率の値の確からしさを表すもの)をA(高い)、B(中程度)、C(やや低い)、D(低い)の4段階にランク付けすることとした上で、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)について、発生領域の評価の信頼度をC(想定地震と同様な地震が領域内で1ないし3回しか発生していないが、今後も領域内のどこかで発生すると考えられる。発生場所を特定できず、地震データも少ないため、発生領域の信頼性はやや低い。)、規模の評価の信頼度をA(想定地震と同様な地震が3回以上発生しており、過去の地震から想定規模を推定できる。地震データの数が比較的多く、規模の信頼性は高い。)、発生確率の評価の信頼度をC(想定地震と同様な地震は領域内で2ないし4回と少ないが、地震回数を基に地震の発生率から発生確率を求めた。発生確率の値の信頼性はやや低い。)と評価し、平成21年3月9日、「長期評価」を一部改訂した際(なお、三陸沖から房総沖の海溝寄りの評価に変更はない。)、上記の信頼度を追加した。このことも、本件地震発生前の時点において、「長期評価」の信頼性に限界があったことを示す事情ということができる。
なお、指定弁護士は、「長期評価」は平成21年3月及び平成23年3月に一部改訂されているところ、本件地震発生前の各改訂作業において、海溝寄り領域を一つの領域として評価したことについて見直しを求める意見は出ておらず、このことは、「長期評価」の信頼性を裏付けている旨主張する。しかしながら、前記のとおり、「長期評価」には、各改訂作業に先立って、評価結果には誤差を含んでいる旨が表紙に記載されていた上、発生領域の信頼度の評価はCのまま変わっていないのであるから、信頼度の見直しが唱えられたのであればともかく、各改訂作業において海溝寄り領域を一つの領域としたことについて見直しを求める意見が出なかったことをもって、「長期評価」の信頼性が裏付けられたことになるわけではない。
8 他の機関の扱い
(1) 防災対策関係
ア 中央防災会議
中央防災会議は、災害対策基本法に基づき、内閣府(本件地震発生当時)に設置された会議であり、防災基本計画を作成し、その実施を推進することなどの事務をつかさどり、地震本部による地震の評価を基に地震対策の方針を定める役割を有するものである。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会は、この中央防災会議に設置された専門調査会であり、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を作成し、その実施を推進することなどを任務としていた。同専門調査会(当時、阿部、島崎及び今村ら多数の地震、津波の専門家らが委員を務
めていた。)は、平成18年1月25日、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」を公表した。同報告書は、北海道及び東北地方を中心とする地域に影響を及ぼす地震のうち、特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目して、防災対策の対象とすべき地震を選定した上で、対象地震による揺れの強さや津波の高さを評価し、この評価結果をもとに被害想定を実施し、予防的な地震対策及び緊急的な応急対策などについて検討し、地震対策の基本的事項について取りまとめたものである。同報告書は、防災対策の検討対象とする地震としては、過去に大きな地震(M7程度以上)の発生が確認されているものを対象としつつ、大きな地震が発生しているが繰り返しが確認されていないものについては、発生間隔が長いものと考え、近い将来に発生する可能性が低いものとして、防災対策の検討対象から除外し、このことから福島県沖・茨城県沖のプレート間地震を除外することとしていた。選定の結果、防災対策の検討対象とする地震は、日本海溝の海溝型地震としては、三陸沖北部の地震、宮城県沖の地震及び明治三陸タイプ地震とされた。上記専門調査会の審議において、阿部は、「多くの研究者は明治の三陸が繰り返すとは思っていませんし、昭和の三陸が繰り返すとは思っていないけれども、あの程度のことは隣の領域で起こるかもしれないぐらいは考えているわけですね。」、長谷川昭東北大学教授は、「私たちが持っているデータ、情報は繰り返し間隔が非常に長いものについては、たまたま当たったものを見ている。それで、たまたま当たっていない方が実は可能性が高いということを皆さん気にしているのだろうと思うのですね。」、杉山雄一独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター長は、「歴史時代に起こったものをそのある地域だけの代表と見るものと、そうではなくて、あるもう少し広いそういうプレートテクトニックな枠組みで見たら共通性があって、もっと広い範囲で評価すべきものと、その両方があるはずであって、それを同じように切ってしまうのはちょっと問題がある」と発言している。島崎も、公判において、過去の地震は未解明な部分があるにもかかわらず、繰り返し起きていると判断した地震に対してのみ防災対策をし、繰り返しの証拠がない地域は無視するというのは科学的根拠がめちゃくちゃである旨の供述をしている。他方、同専門調査会の座長の溝上恵東京大学名誉教授は、審議の過程で、「推本の確率論というのはどうももう一つ私個人としては信ぴょう性のあるものから、ないものから、全く玉石混交で、どれがどうやら、もうちょっときちんとしないと防災にすぐ取り入れるにはいささか問題があることだというふうに私は理解しています。」と発言している。
イ 福島県「津波浸水想定区域図」
福島県は、津波防災の専門家らからなる福島県沿岸津波浸水想定検討委員会を設置し、その検討を経て、平成19年7月、「福島県沿岸津波浸水想定区域図」を作成し、公表した。同区域図は、想定地震として、①宮城県沖地震(Mw8.2、中央防災会議が採用したモデルを想定断層モデルとする。)を宮城県沖に、②明治三陸タイプ地震(Mw8.6、中央防災会議が採用したモデルを想定断層モデルとする。)を三陸沖の海溝軸付近に、③福島県沖高角断層地震(Mw7.7、1938年福島県東方沖(塩屋沖)群発地震の一つをモデルにしたものでモーメントマグニチュード推定値のうち最大値を採用したもの。)を福島県沖に、それぞれ設定した。本件発電所においては、このうち③の地震による津波の影響が最も大きく、防波堤の内側では構造物の効果を考慮した場合に4m盤の最大浸水深が概ね0.5m以下であった。上記委員会の検討において、福島県沖の海溝寄りの領域で明治三陸タイプ地震が起こることを想定すべきであるとの意見が述べられることはなかった。
ウ 茨城県「津波浸水想定区域図」
茨城県は、茨城沿岸津波浸水想定検討委員会(今村、佐竹らが委員を務めていた。)を設置し、その検討を経て、平成19年10月、「津波浸水想定区域図」を公表した。同区域図は、将来発生が予測される津波について、茨城沿岸地域を対象とした津波シミュレーションを行うとともに、その結果を利用して津波浸水想定や被害想定を実施するものであり、津波防災対策の基礎資料として活用することを目的とするものであった。同区域図は、想定地震として、①中央防災会議の検討で繰り返し性が確認されている明治三陸タイプ地震(Mw8.6、中央防災会議が採用したモデルを想定断層モデルとする。)を三陸沖の海溝軸付近に、②繰り返し性は確認されていないが、茨城沿岸の既往最大津波をもたらした延宝房総沖地震(Mw8.29、中央防災会議試算の波源のすべり量を津波痕跡を踏まえ1.2倍した茨城県独自のモデルを想定断層モデルとする。)を茨城県及び千葉県沖の海溝軸付近に、それぞれ設定した。上記委員会の検討において、房総沖で明治三陸タイプ地震が起こることを想定すべきであるという意見が述べられることはなかった。
(2) 保安院
前記のとおり、保安院においては、「長期評価」が公表された翌月の平成14年8月、東京電力の担当者から、「長期評価」を確率論的津波ハザード解析の研究におけるロジックツリーの分岐の一つとして扱う方針である旨の説明を受けた際、その方針に特段の異論を述べず、その後も、前記のとおり、新知見ルールにより、「長期評価」を安全審査に取り込むべき最新の知見(「新知見情報」又は「新知見関連情報」)とは扱わず、耐震安全性評価に関連する「参考情報」として扱い、本件地震発生までの間に、東京電力に対し、直ちに「長期評価」の見解に基づく津波に対する対策工事を実施し、その対策が完了するまでは本件発電所の運転を停止するよう求めたこともなかった。
(3) 他の電力会社、基盤機構
ア 東北電力は、宮城県牡鹿郡女川町の太平洋岸に女川原子力発電所を設置していたところ、平成20年3月には、「長期評価」の見解に基づいて明治三陸地震の波源(Mw8.3)を日本海溝寄りの宮城県沖と福島県沖をまたぐ位置に設定した場合、同発電所における津波最高水位がO.P.+18.16mとなり、O.P.+14.8mの敷地が浸水する旨の計算結果を得ていたが、その後の耐震バックチェック報告においては、「長期評価」の見解を取り込まずに、明治三陸地震の波源モデルを津波評価技術に示された領域に設定して津波水位に関する安全性評価を行い、本件地震発生までの間、津波に対する安全性が確保されていないことを理由に女川原子力発電所の運転を停止することはなかった。そして、原子炉施設等に関する検査、原子炉施設等の設計に関する安全性の解析及び評価の業務を行う独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「基盤機構」という。)は、東北電力による上記バックチェック報告の内容についてクロスチェック解析を実施し、平成22年11月30日、東北電力の報告が妥当であると判断した。
イ 日本原電は、茨城県那珂郡東海村の太平洋岸に東海第二発電所を設置していたところ、平成20年2月には、「長期評価」の見解に基づいて明治三陸地震の波源(Mw8.3)を日本海溝寄りの茨城県沖に設定した場合、同発電所における津波最高水位がH.P.(日立港工事用基準面)+12.24mとなり、H.P.+8.89mの主要施設の敷地が浸水する旨の計算結果を得ていたが、本件地震発生までの間、津波に対する安全性が確保されていないことを理由に東海第二発電所の運転を停止することはなかった。もっとも、日本原電は、「長期評価」の見解(ただし、日本海溝沿いを北部と南部に分けて波源を設定するもの)に基づく津波を対象に対策工事を実施することとし、平成21年5月末までに地盤改良工事で発生した排泥を利用した盛土工事を、同年9月末までに建屋外壁開口部の改造工事を、同年10月末までに海水ポンプ室側壁の設置工事をそれぞれ完了したが、上記の盛土工事によっても、「長期評価」の見解(北部と南部を分けずに波源を設定するもの)に基づく津波が建屋敷地へ遡上することを防ぐことができるわけではなかった。
(4) 小括
以上のとおり、「長期評価」の見解は、本件地震発生前の時点において、一般防災においては取り入れられず、原子力発電所の津波対策の場面においても、保安院は「参考情報」として扱い、これを積極的に取り入れるよう求めず、基盤機構もこれを取り入れるよう求めたことはなく、他の電力会社がこれをそのまま取り入れることもないなど、原子炉の安全対策を含む防災対策を考えるに当たり、取り入れるべき知見であるとの評価を一般に受けていたわけではなかったといわざるを得ない。
9 津波ハザード解析の結果
前記のとおり、平成16年12月に東京電力が東電設計から受領した「既設プラントに対する津波ハザード解析委託報告書」において、本件発電所の1号機から4号機までの津波ハザード曲線(近地津波及び遠地津波)は、津波高さO.P.+10mの年超過確率が、フラクタイル算術平均で10のマイナス5乗よりもやや低い頻度であり、また、平成20年6月10日に被告人武藤に示された津波ハザード曲線は、主要建屋が13m盤に設置された6号機のものであったが、フラクタイル算術平均で10のマイナス4乗と5乗の間の頻度であった。一方、平成18年3月に原子力安全委員会安全目標専門部会が定めた発電用軽水型原子炉施設の性能目標の定量的な指標値案は、前記のとおり、炉心損傷頻度を10のマイナス4乗/年程度、格納容器機能喪失頻度を10のマイナス5乗/年程度とするものであった。
原子力発電所における津波に対する確率論的リスク評価の実施基準は、本件事故前には存在していなかったところ、一般社団法人日本原子力学会は、本件事故後の平成24年2月、「原子力発電所に対する津波を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準」を策定した。これは、津波についての確率論的リスク評価の開発、整備及び標準策定活動が課題とされていたという状況を踏まえ、津波についての確率論的リスク評価の実施基準を規定したものである。その評価手順は、津波ハザード評価のほか、ある事象が起きたときに建屋・機器が故障に至るかどうかを評価する建屋・機器フラジリティ評価、故障したときに炉心が溶けるような事故に至るかどうかを評価する事故シーケンス評価の3段階の評価を行うというものであり、外的事象に関する一般的な評価手法である。本件事故前、東京電力に報告されていた前記の津波ハザード解析結果は、上記の評価手順のうち、第1段階の津波ハザード評価の結果のみを示したものであるから、第2段階の建屋・機器フラジリティ評価及び第3段階の事故シーケンス評価を経ずに、直ちに前記の指標値案における炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度と対照されるべきものとはいえない。
しかし、我が国においては、本件地震発生前、原子力発電所の敷地を浸水させないいわゆるドライサイトの考え方に基づいて原子力発電所が設計されていたから、津波が設計上の想定を上回り敷地を超えて遡上すると建屋や機器側の余裕がないため一気に炉心損傷又は格納容器機能喪失の危険が高まる状況(クリフエッジ)にあったということができる。そうすると、津波に対する確率論的リスク評価の手法が確立されていなかった本件事故前においても、津波ハザード解析結果は、その成熟性に留意しつつ、津波対策の検討に当たり参照し得るものであったということができる。
もっとも、本件発電所の津波ハザード解析は、ロジックツリーの分岐に重み付けをするに当たり、前記のとおり評価に限界のあるアンケート結果を参考にしているから、その解析結果の評価にもまた限界があるものといわざるを得ない。また、この点を措くとしても、前記の津波ハザード解析結果によれば、本件発電所の1号機から4号機までの津波ハザード曲線は、津波高さO.P.+10mの年超過確率がフラクタイル算術平均で、10のマイナス5乗よりもやや低い頻度にとどまっており、これは通常設計事象として取り込むべき頻度であるとまでは必ずしも考えられていなかった。そうすると、本件発電所の津波ハザード解析の結果も、「長期評価」の信頼性が高いことを示していたとはいえない。
10 小括
以上の検討によれば、平成23年3月初旬の時点において、「長期評価」は、Mt8.2前後の津波地震が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとすることについて、具体的な根拠を示さず、海溝寄り領域内の海底地殻構造の違いに対する有効な応答も示しておらず、そのため、地震学や津波工学の専門家、実務家、さらに内閣府によって疑問が示され、中央防災会議や地方自治体の防災計画にも取り込まれず、保安院による安全審査や基盤機構によるクロスチェック解析にも取り込まれなかったものである。そして、東京電力の土木グループ担当者、他の関連グループの担当者だけでなく、東京電力以外の原子力事業者からも、直ちにこれに対応した対策工事を実施し、対策工事が完了するまでは原子炉を停止する必要があるとの認識が示されることはなかった。さらに、本件発電所の津波ハザード解析の結果も、「長期評価」の信頼性が高いことを示すものとはいえない。そうすると、平成23年3月初旬の時点において、「長期評価」の見解が客観的に信頼性、具体性のあったものと認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。
そうすると、平成20年6月10日の被告人武藤への説明、平成21年4月ないし5月頃の被告人武黒への説明のいずれもがそうであったように、平成23年3月初旬までの時点においては、「長期評価」の見解は具体的な根拠が示されておらず信頼性に乏しいと評価されていたところ、そのような「長期評価」に対する評価は、相応の根拠のあるものであったというべきである。
第7 運転停止措置の容易性又は困難性
1 はじめに
以上のとおり、指定弁護士が予見可能性の前提となる「重要な契機」として主張している事実関係を中心に事実を認定、評価してきたが、前記のとおり、予見可能性の有無を判断するに当たっては、結果回避義務として求められている作為の負担や困難性等についても考慮する必要があるため、この点について検討を加えておく。
2 運転停止のために必要な手続等
本件地震発生前、本件発電所の原子炉の運転を停止するための措置としては、通常、原子炉圧力容器内の燃料集合体と燃料集合体との間に、核分裂によって生じた中性子を吸収する物質で作られた制御棒を挿入するという方法が採られていたところ、このような操作それ自体は特段の負担や困難を伴うものではなかった。
しかしながら、本件地震発生前、本件発電所は、法令に基づく運転停止命令を受けておらず、かつ、事故も発生していないのであって、そのような状況において、前記の多重的な対策が完了するまでの相当な期間にわたって原子炉の運転を停止することとなれば、東京電力の社内においては、常務会における審議、社長の決定、取締役会における審議及び決議という手続が必要であった。加えて、代替電源の確保、火力発電に用いる燃料の調達、燃料の輸送手段の確保、燃料購入費の調達、収支計画の見直し、電気料金の見直し、送電系統への影響、二酸化炭素排出量増加に伴う排出権の確保等、多岐にわたる検討が必要であった。これらの手続、検討のためには、社内の関係各部門に対して、原子炉を停止することについて事前に説明し、その理解を得ておく必要があった。
また、東京電力の社外に関しても、まずは本件発電所を設置している地元自治体に対し、原子炉を停止することについて事前に説明し、その了承を得る必要があった。そして、本件発電所の運転を停止するのであれば、福島県双葉郡楢葉町と富岡町にまたがり、本件発電所の約12km南の太平洋岸に位置しており、O.P.+12mの敷地に主要建屋が設置されている福島第二原子力発電所も共に停止することが予想され、その場合には、同発電所を共同開発し、かつ、電力の広域融通をしている東北電力に対しても、同様に事前に説明し、その了承を得る必要があった。
さらに、東京電力は、前記のとおり、電気事業法に基づいて電力供給義務を負っているところ、本件発電所の運転停止が供給計画の変更(同法29条)や電気料金の値上げにもつながりかねないこと、同時に、平成19年3月に策定された「エネルギー基本計画」の中で「原子力発電は、供給安定性に優れ、かつ、発電過程において二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源であり、エネルギー安全保障の確立と地球温暖化問題との一体的な解決を図る上で要となるものである。」などとされ、本件地震発生当時は、政府によって地球温暖化対策として原子力発電を積極的に推進する政策がとられていたことから、資源エネルギー庁、原子力安全委員会、保安院といった行政機関側に対しても、事前に同様の説明をし、その了承を得る必要があった。
以上のように、本件発電所の運転停止措置は、被告人らの一存で容易に指示、実行できるようなものでは到底なく、東京電力の社内はもとより、社外の関係各機関に対して、本件発電所の原子炉を停止することの必要性、合理性について具体的な根拠を示して説明し、その理解、了承を得ることが必須であったものと認められ、そのような意味で、手続的に相当な負担を伴うものであったとみざるを得ない。
3 運転停止措置の技術的な困難性
指定弁護士の主張するところによれば、本件事故を確実に回避するためには、前記のような方法で単に原子炉の運転を停止するだけでは足りず、平成23年3月初旬までに、本件発電所の各号機の原子炉を停止した上、炉心が露出する状態となることを防ぎ、かつ、圧力容器内に水を補給しやすくするために、格納容器と圧力容器の蓋を開けて、圧力容器内に水を満たした状態にしておく必要があったというのである。確かに、原子炉を停止して5日程度経過すれば、原子炉停止直後に比べ燃料の崩壊熱は格段に小さくなっているので、圧力容器内の水位が急激に低下することはなく、また、格納容器と圧力容器の蓋が開放されていれば、圧力容器内への水の補給も容易であったから、本件地震による津波が襲来し、10m盤上のタービン建屋等へ浸入して、交流電源及び直流電源の喪失により炉心を「冷やす機能」を喪失したとしても、圧力容器内への注水が行われるまでに炉心露出や炉心損傷に至ることはなく、本件事故を回避することができたと考えられる。しかしながら、このような運転停止の方法は、本件事故の発生経過を調査、検討した結果を踏まえた本件事故後の知見に基づくものであって、本件地震発生前の時点において、炉心損傷を防ぐために、圧力容器内の水位を高くしておくとか、放射性物質を「閉じこめる機能」を犠牲にして格納容器と圧力容器の蓋を開放したままにしておくといった発想に至るのは、実務的には相当に困難なものであったと認められる。すなわち、指定弁護士の主張する運転停止の具体的な方法は、技術的観点からみても相当に困難なものであったと考えざるを得ない。
第8 予見可能性の検討
1 本件において業務上過失致死傷罪が成立するために必要な予見可能性
平成23年3月初旬の時点において、原子炉等規制法は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うことをなど目的とし(1条)、実用発電用原子炉を設置しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならず(23条)、同大臣は、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子炉施設の位置、構造及び設備が原子炉による災害の防止上支障がないものであること等の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない(24条)と定めていた。同法の定める原子力施設の安全性に関する審査は、原子力工学を始めとする多方面にわたる高度な最新の科学的、専門的知見に基づく総合的な判断が必要とされるものであるが、自然現象を原因とする原子力災害については、前記のとおり、その原因となる自然現象の発生メカニズムの全容解明が今なお困難で、正確に予知、予測することもまた困難である。そして、前記のとおり、原子力安全委員会が平成18年9月に策定した発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(新指針)は、耐震設計上重要な施設の設計について、「地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計」されることを求め、また、地震随伴事象に対する考慮としても、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがない」ことを求めており、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがある」全ての地震動による地震力、あるいは、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある」全ての津波についてではなく、いずれも、そのように「想定することが適切な」地震動による地震力又は津波に対して、施設の安全機能が損なわれることのないことを求めている。また、地震動については、施設の設計に当たり、「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われることを求めているのであって、必ずしも地震動や津波によって施設の安全機能が損なわれる可能性が皆無もしくは皆無に限りなく近いことまでを要求しているわけではなかった。また、保安院は、前記のとおり、平成21年5月に新知見ルールを定め、報告を受けた科学的、技術的知見については、これを耐震安全性評価及び耐震裕度への反映が必要な「新知見情報」、耐震安全性の再評価や耐震裕度の評価変更につながる可能性のある「新知見関連情報」、耐震安全性評価に関連する「参考情報」に整理・分類することとしており、社会に存在する科学的知見又は技術的知見の全てを施設の安全性確保に反映させることまでを想定しているわけではなかった。
以上のような原子炉の安全性確保についての原子炉等規制法及びこれを受けた審査指針等における規制の在り方からすると、平成23年3月初旬の時点において、同法の定める原子力施設の自然災害に対する安全性は、どのようなことがあっても原子炉内の放射性物質が外部の環境に放出されることは絶対にないといったレベル、あるいはそれとほぼ同じレベルの、極めて高度の安全性をいうものではなく、最新の科学的、専門的知見を踏まえて、合理的に予測される自然災害を想定した安全性であって、そのような安全性の確保が求められていたものと解される。そして、このことは、保安院等が東京電力やその他の原子力事業者に対し、「長期評価」を取り入れた対策を直ちに取ることを積極的に求め、さらには対策が完了するまでは原子炉の運転の停止を求めることまではしなかったことなどからみても、少なくとも平成23年3月初旬までの時点では、実際上の運用としても同様であったと解される。以上に加えて、本件発電所の運転停止という結果回避措置それ自体に伴う手続的又は技術的な負担、困難性として先に指摘したところも併せ考えれば、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性については、当時得られていた知見を踏まえて合理的に予測される程度に信頼性、具体性のある根拠を伴うものであることが必要であったと解するのが相当である。
2 平成23年3月初旬の時点における被告人らの認識
(1) 被告人武藤の認識
被告人武藤は、前記のとおり、平成17年6月以降、原子力・立地本部副本部長、同本部本部長を務めており、本件発電所における想定津波水位に関して、被告人ら3名の中で最も多くの情報に接している。
まず、平成20年6月10日、吉田らから、以下の事実について説明を受けた。すなわち、プレート間大地震(津波地震)が海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性があるとする「長期評価」が公表されたこと、これをロジックツリーの分岐の一つとして扱い、重み付けアンケートの結果、地震学者の平均で上記地震が上記領域内のどこでも発生するが0.6、福島県沖では発生しないが0.4であり、その結果を踏まえた本件発電所6号機の津波ハザード曲線は、O.P.+10mの年超過確率が10のマイナス4乗と5乗の間、O.P.+13mの年超過確率が10のマイナス5乗と6乗の間であること、明治三陸地震モデルによるパラメータスタディの結果、本件発電所における最高津波水位がO.P.+15.7m、鉛直壁に当たる津波高さが最大O.P.+約20mになること、耐震バックチェックの審査に関与している専門家が「長期評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り込むべきと言っているので、土木グループとしては取り込まざるを得ないと考えていること、一方で、取り込んだ場合、耐震バックチェック最終報告時に同見解を前提とした津波対策工事を完了させることは困難であり、そのことの対外的な説明が問題となることなどである。また、その後、耐震バックチェックの過程で本件発電所の津波対策に影響を及ぼし得るものとして、貞観地震があることに関しても説明を受けた。
その一方で、被告人武藤は、吉田から、「長期評価」は波源領域の設定につき明確な根拠を示していない点などに問題があるといった理由から、信頼性がなく、海溝沿いの津波に対する対応については原子力事業者間でも統一されていない旨の説明を受けた。また、被告人武藤は、平成20年7月31日、吉田らから説明を受けた際、「長期評価」の見解の扱いについて、これを直ちに安全対策に取り入れる旨の判断はせず、その扱いについて土木学会の検討に委ねることを指示したが、このような方針については、その席上を含め、平成23年3月初旬の時点までに、東京電力社内はもとより、他の原子力事業者、専門家、行政機関からも、直ちに対策工事に着手し、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきであるといった異論が出ているというような報告がなされたという事実は窺われない。そして、貞観地震津波についても、「長期評価」と併せて土木学会で審議されるという説明を受けた。
(2) 被告人武黒の認識
被告人武黒は、平成20年8月初旬頃、被告人武藤から、「長期評価」の見解に従って福島県沖の日本海溝沿いに津波の波源を置いて計算したところ、本件発電所で高い津波水位となったこと、これを受けて当該見解について土木学会に検討を依頼し、結果が出れば、その結果に応じた対策工事を行う方針であることについて報告を受けた。次に、平成21年4月又は5月頃、吉田から、「長期評価」の見解に基づいて明治三陸地震の波源を福島県沖に設定すると、本件発電所の最高津波水位がO.P.+15.7mとなったことなどを受け、「長期評価」の取扱いについて土木学会に検討を依頼しているところ、その検討には数年を要すること、この方針については主要な学者の了承を得ていることについて報告を受けた。そして、同年6月頃には、酒井から、「長期評価」の概要及び土木学会の検討には約3年を要することの説明を受け、その後においては、新たに問題となっている貞観地震についても「長期評価」の見解と併せて土木学会で審議されることなどについて説明を受けた。
その一方で、被告人武黒は、被告人武藤からは、「長期評価」には分からない点があり、だからこそ対策工事の着手に先立ち、土木学会にその取扱いについて検討を依頼する必要性があることの報告を受け、吉田らからは、「長期評価」は津波地震が海溝寄り領域内のどこでも起きるとする具体的な根拠を示しておらず、地震本部自らもどこでも起きるとする点の信頼度をCクラスに分類していることに加え、中央防災会議も「長期評価」の見解を採用していないことを報告されるなどした。
(3) 被告人勝俣の認識
被告人勝俣は、平成21年2月11日、中越沖地震対応打合せにおいて、土木学会評価手法(すなわち津波評価技術)の使い方をよく考えて説明しなければならない、「(O.P.+6.1mより)もっと大きな14m程度の津波が来る可能性があるという人もいて」、前提条件となる津波をどう考えるか、そこから整理する必要がある旨の吉田の発言を聞き、少なくとも本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性を示唆する見解が存在するという程度のことは認識していたものと認められる。
その一方で、被告人勝俣は、14mという数値の根拠や信態性についての説明や報告は受けておらず、したがって、「長期評価」の内容や、その見解に基づいて本件発電所の津波高さの数値解析を実施した結果、最高津波水位がO.P.+15.7mとなったことなどの具体的な事項についての認識は有していなかった。
(4) 小括
以上のとおり、被告人武藤及び被告人武黒は、「長期評価」の概要及び本件発電所について「長期評価」の見解に基づいた津波の数値解析を行うと、その最高津波水位がO.P.+15.7mになることなどを認識していたものの、他方で、吉田らから、その数値解析結果の基礎となった「長期評価」の見解そのものについて、根拠がなく、信頼性も低い旨の報告を受け、そのように認識していた。また、被告人勝俣は、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性がある旨を示唆する見解があるという程度の認識は有していたものの、そのような見解の内容や、どの程度の信頼性があるかといったことについては、認識してはいなかった。加えて、平成23年3月初旬の時点までに、被告人ら3名のいずれかに対して、東京電力社内の担当者、他の原子力事業者、専門家、行政機関から、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性があり、本件発電所の安全性には疑義があるとして、直ちにその対策工事に着手すべきであり、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきであるといった指摘があったとの報告がなされた事実も窺われない。
以上からすると、被告人ら3名は、報告を受けた時期の先後や内容の濃淡に差があったにせよ、いずれも、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性があり得る旨を示す情報についての報告は受け、そのような情報についての認識まではあったと認められるものの、平成23年3月初旬までの時点において、10m盤を超える津波が襲来する可能性について、信頼性、具体性のある根拠を伴っているという認識は有していなかったものと認められる。
なお、被告人武藤は、さらに、耐震バックチェックの審査に関与している専門家が「長期評価」の見解を耐震バックチェックに取り込むべきとの意見を述べていることなどから、土木グループとしても取り込まざるを得ないと考えている旨の報告を受け、そのことを認識していたが、その土木グループの担当者や、土木グループの上位組織である対策センターのセンター長である山下、その上位組織である原子力設備管理部の部長である吉田から、「長期評価」に信頼性はない旨の説明を受けていたこと、耐震バックチェックは、既存の原子力発電所の安全性が確保されていることを前提に、安全性の一層の向上を図るために行われるものであるから、「長期評価」の見解を直ちに耐震バックチェックには取り入れず、まずはその取扱いについての検討を土木学会に委託するという被告人武藤自身の打ち出した方針が、東京電力社内での反対はもとより、他の原子力事業者、専門家、行政機関といった社外からの異論もないまま受け入れられていたことなどに照らせば、「長期評価」を耐震バックチェックに取り入れざるを得ないという土木グループの判断があったからといって、10m盤を超える津波襲来の可能性に関する被告人武藤の認識に影響を与えるものとは認められない。
また、被告人ら3名は、いずれも、中越沖地震対応打合せにおける報告等により、耐震バックチェック最終報告書の提出時期と津波対策工事完了の時期が問題となり、最終報告書提出時に対策工事が完了していない場合、本件発電所の運転停止のリスクがあることを認識していた。しかしながら、被告人らの認識していたこのような運転停止のリスクは、本件発電所の安全性が実質的に損なわれることを理由とするものではなく、前記のとおり、対外的な説明が困難となって、本件発電所の運転停止に追い込まれかねないというものであって、このようなリスクの認識も、10m盤を超える津波襲来の可能性に関する被告人らの認識に影響するものとはいえない。
3 予見可能性の存否
(1) 「長期評価」等を基礎とする予見可能性
以上検討したところによれば、被告人ら3名は、条件設定次第では、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来するとの数値解析結果が出る、もしくは、そのような津波襲来の可能性を指摘する意見があるということは認識していたのであるから、被告人ら3名において、10m盤を超える津波の襲来を予見する可能性がおよそなかったとはいい難い。しかしながら、被告人武藤及び被告人武黒は、そのような数値解析結果については、条件設定の基礎となった「長期評価」の見解それ自体に信頼性がなく、適切な条件設定は専門家集団である土木学会によって検討途上である旨認識しており、現に「長期評価」の見解は、前記のとおり、平成23年3月初旬までの時点においては、客観的に信頼性があるとみるには疑義の残るものであった。また、被告人勝俣は、10m盤を超える津波襲来の可能性を指摘する意見があるという程度の認識を有していたに過ぎず、「長期評価」の内容等も認識していなかったものである。そうすると、前記の一連の事実経過を踏まえて考えても、被告人ら3名はいずれも、平成23年3月初旬までの時点においては、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性について、信頼性、具体性のある根拠を伴っているとの認識がなかったとみざるを得ない。
加えて、他の原子力事業者、原子力安全に関わる行政機関、防災対策に関わる行政機関や地方公共団体のいずれもが、「長期評価」を全面的に取り入れることのない状況において、「長期評価」の取扱いについて、貞観地震津波と併せて土木学会の審議に委ねるとした方針に対して、東京電力社内はもとより、他の原子力事業者、関連分野の専門家、さらには原子力安全に関わる行政機関から、「長期評価」の見解に基づいて直ちに安全対策工事に着手し、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきであるといった異論が述べられているというような情報に接することもなかったのであるから、被告人ら3名にとって、前記のような数値解析結果が出たからといって、直ちにこれに対応した対策工事に着手し、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止しなければ、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来し、炉心損傷等の重大事故につながる危険性があるとの認識は持ち得なかったとしても、不合理とはいえない。そして、このことは、上記のとおり、他の原子力事業者、行政機関、地方公共団体のいずれにおいても、「長期評価」を全面的に取り入れることがなく、東京電力社内、他の原子力事業者、専門家、行政機関のどこからも、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきである旨の指摘もなかったことに照らせば、これら関係者にとっても同様であったとみるべきであって、平成23年3月初旬までの時点における原子力安全対策の考え方からみて、被告人ら3名の対応が特異なものであったとはいい難く、逆に、このような状況の下で、被告人ら3名に、10m盤を超える津波の襲来を予見して、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきである。
以上のとおりであり、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性について、被告人ら3名がそれぞれ認識していた事情は、当時得られていた知見を踏まえ上記のような津波の襲来を合理的に予測させる程度に信頼性、具体性のある根拠を伴うものであったとは認められない。したがって、被告人ら3名において、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来することについて、本件発電所の運転停止措置を講じるべき結果回避義務を課すに相応しい予見可能性があったと認めることはできないといわなければならない。
(2) 情報収集義務(情報補充義務)
ところで、指定弁護士は、被告人らが、一定の情報収集義務(情報補充義務)を尽くしていれば、10m盤を超える津波の襲来は予見可能であった旨主張する。しかしながら、これまでに検討したとおり、前記の数値解析の基礎となった「長期評価」の見解は、平成23年3月初旬までの時点においては客観的にみてその信頼性に疑義があり、また、東京電力社内はもとより、他の原子力事業者、専門家、原子力安全に関わる行政機関からも、直ちに「長期評価」に基づく対策工事に着手し、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきであるといった指摘はされておらず、さらに「長期評価」の見解を貞観地震津波と共に検討していた土木学会第4期津波評価部会も、具体的な波源モデルや数値計算の手法については未だ審議の途上にあった以上、被告人らが更なる情報の収集又は補充を行っていたとしても、上記の内容以上の情報が得られたとは考え難く、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来する可能性につき、信頼性、具体性のある根拠があるとの認識を有するに至るような情報を得ることができたとは認められないから、指定弁護士の主張を検討しても、予見可能性についての前記判断は動かない。そもそも、被告人らの東京電力における地位と権限は前記のとおりであり、会社の規模、取扱業務の多様性と専門性に加え、会社の態勢としても業務分掌制が採られ、一次的には担当部署に所管事項の検討、対応が委ねられていたことなどに照らせば、前記認定の一連の事実経過のとおり、土木グループ等の担当部署が情報収集や検討等を怠り、あるいは収集した情報や検討結果等を被告人らに秘匿していたというような特殊な事情も窺われないのであるから、被告人ら3名は、基本的には担当部署から上がってくる情報や検討結果等に基づいて判断をすればよい状況にあったのであって、被告人らに情報収集又は情報補充の懈怠が問題となるような事情は窺われない。
第9 結語
本件事故の結果は誠に重大で、取り返しのつかないものであることはいうまでもない。そして、自然現象を相手にする以上、正確な予知、予測などできないことも、また明らかである。このことから、自然現象に起因する重大事故の可能性が一応の科学的根拠をもって示された以上、何よりも安全性確保を最優先し、事故発生の可能性がゼロないし限りなくゼロに近くなるように、必要な結果回避措置を直ちに講じるということも、社会の選択肢として考えられないわけではない。しかしながら、これまで検討してきたように、少なくとも本件地震発生前までの時点においては、賛否はあり得たにせよ、当時の社会通念の反映であるはずの法令上の規制やそれを受けた国の指針、審査基準等の在り方は、上記のような絶対的安全性の確保までを前提としてはいなかったとみざるを得ない。確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。
以上の次第で、被告人らにおいて、本件公訴事実に係る業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能性があったものと合理的な疑いを超えて認定することはできず、被告人勝俣については代表取締役会長としての、被告人武黒についてはフェローとしての、それぞれの責任主体性ないし業務性の問題について立ち入るまでもなく、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、被告人らに対し刑事訴訟法336条によりいずれも無罪の言渡しをする。
(裁判長裁判官 永渕健一 裁判官 今井理 柏戸夏子)
別紙 被害者目録1~4≪略≫